アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ!

| 山行期間 | 2018年4月14日夜~15日 |
|---|---|
| メンバー | KNS, SGY, FRZ, KSU, HYS, AMM, NKG, ICK, BBA |
| 山行地域 | 金剛山 |
| 山行スタイル | 担荷 |

78期生、第3回目の山行は金剛山南尾根。
78期として、初めての前泊山行。そして、初めての歩荷トレーニングです。
数日前の天気予報では春の嵐が吹き荒れる大荒れ予報。
天気の回復を願うも虚しく、当日は予報通りの雨・・・
小雨の降る中、PM21:00頃、紀見峠駅より出発です。
仕事の都合などで、前泊から参加出来たのはリーダー1名とBチームより3名。
ヘッドランプの灯りを頼りにPM21:30頃紀見峠に到着。
テント設営後、ずぶ濡れの身体のままテントに潜り込みます。
テントの中での生活をご指導頂きながら、各々寝床を作り終え、リーダー自家製の梅酒を頂きながら小宴会のスタート(KNSさん馳走様でした^ ^とても美味しかったです!)
先輩の貴重なお話を聞かせて頂きながら、これから先の自分達の山行に胸を躍らせつつPM23:15頃に就寝。
PM24時頃、次第に雨足が強くなって来た模様。
雨の中のテント泊で寒くないか不安でしたが、思いの外テント内は暖かく快適に眠りにつく事が出来ました。
AM5:30起床。前日から変わらず雨は降り続いている様子でしたが、テントの外からは鳥の鳴き声が聞こえて心地良かったです。
寝床を整え、直ぐに食事の準備にかかります。
6時40分頃には撤収を終了し、トイレの軒下で暫し雑談。
AM7時半頃、紀見峠を出発し当日参加組との合流地点である山の神を目指します。
8時5分頃に当日参加組であるリーダー1名、Bチーム4名と合流。
全メンバーで雨の中、今回の目的である歩荷トレーニング用の石を探しながら歩きます。
山の神を少し越えた所で、歩荷に丁度良さそうな石がチラホラ。
未知の重さにビクビクしながら各々ザックに石を詰め込み、いよいよ歩荷トレーニングのスタートです!!
初めてという事もあり、女子は15キロ。
それに比べ男子のザックは20半ば~30キロと強者揃い!
AM8時15分歩荷トレーニングスタート。
肩にザックの重みがずしりときます。
急登が続きますが、皆黙々と足を進めてAM9時05分頃、西の行者を過ぎ、AM9時10分頃に一回目の休憩を取りました。
AM9時27分タンボ山付近に差し掛りますが、雨は依然降り続いたままで、寧ろ強くなっているような気もします。
AM9時40分杉尾峠を過ぎ、AM10時頃行者杉で2回目の休憩を挟みました。
行者杉には雨を凌げる屋根があり、テーブルとベンチもあって各々行動食を取ったり、雑談しながら休憩。
しかし、降り続く雨に濡れた身体は予想以上に冷えている様で休憩中はとても寒く、身体はガタガタと震えていました。
私以外のメンバーからも「寒い寒い」という声が聞こえます。
慣れないザックの重さと降り続ける雨で心が折れそうになりながらも、AM10時35分には神福山、AM10時50分には千早峠を過ぎ、AM11時には3回目の休憩を挟みました。
この頃には、身体は冷え切り「休憩したい」という気持ちよりも「休憩を終えて、早く動きたい」という気持ちの方が強かったです。
最後の力を振り絞り、皆んなで励まし合いながら金剛山を目指します。
AM11時55分には中葛城山を過ぎ、PM12時頃に久留野峠、PM12時40分には伏見峠に到着。
伏見峠を越えた辺りから見慣れた景色が広がり、メンバーの顔にも笑顔が戻ります。
皆んなでワイワイと話しながらPM13時20分頃、金剛山の山頂広場に到着しました。
鞄の中の石はいつ無くなるんだろう…という気持ちを抱きながら、下山はタカハタ道から。
少し歩いた所で待ちに待った石を捨てましょう!の声!背中の荷物も軽くなり、皆んなでワイワイと話しながら沢沿いの道を下ります。
最後のご褒美に腰折れ滝を眺め、PM14時30分に初めてのテント泊、歩荷トレーニングが終了しました。
今回は雨の中でのテント泊、歩荷トレーニングとなりましたが、色々と学ぶ事も多く、本当にいい経験が出来ました。
雨の中、ご指導して下さったリーダーの皆様、本当にありがとうございます。
この経験を生かしながら、78期Bチーム、力を合わせて一年間頑張って行きたいと思います。
(HYS記)
<行動記録>
4/14夜 南海紀見峠駅21:00~紀見峠21:30
4/15 紀見峠7:30~山の神8:05~行者杉10:00~久留野峠12:00~金剛山13:20~タカハタ道~登山口14:30
| 山行期間 | 2018年4月1日 |
|---|---|
| メンバー | KNS, YDA, NKG, FRZ, HYS, AMM, ICK |
| 山行地域 | 紀泉アルプス |
| 山行スタイル | ハイキング |

78期Bチームの第2回山行は、紀泉アルプスです。
リーダーも含めて7人でのハイキングとなりました。
集合場所はJR山中渓駅。天候は晴れ。
朝から気温が高く前回より薄手の服装で参加。
山中渓駅周辺の桜の木はどれも満開で、多くの観光客が下車されてました。一番良い時期にきたみたいです。
9:00にサブリーダーを先頭でスタート。
コースタイムが8時間40分と長時間の縦走となるため足が耐えられるか心配です。
気温が高いため、登り始めてすぐに他の登山客が止まって服装調節してます。私達もタイミングをみて調節。
しばらく急登が続き9:35第一パノラマ展望台へ到着。
展望台という名称の通り素晴らしい景色で気分も盛り上がり雲山峰へ向けて出発。
10:55 雲山峰へ到着。ここで飲み物や行動食をとり各々小休憩。
気温が高いため水の消費が早く、下山まで足りるかな?と思いつつゴクリ。
11:10井関峠へ向けて出発。地図と案内板を見比べながら井関峠方面へ進み11:45 井関峠に到着。
家で調べてきたルートと違うルートを歩いていたようでしたが、良く分かりませんでした。
みんなで4月末の春合宿の食事や装備、集合場所など話をしました。
一人で登る時には考えていなかった事も沢山あり、前回のルームで教えてもらったグループで歩くメリット・デメリットを思い出しながら歩きました。
付近の山々は、桜が満開でどの稜線も素敵な景観が広がっていました。
札立山~飯盛山を越えた後半は、海の景色がプラスされ気持ちが晴れ晴れとしました。
この日は一日中暑く日差しも強かったのでバテ気味でしたが何とかゴールの岬公園駅へ到着する事ができました。
リーダー、サブリーダーの方には大変お世話になりました。
ありがとうございました。
(ICK記)
<行動記録>
JR山中渓駅9:00~第一パノラマ展望9:35~雲山峰11:10~大福山12:20~札立山13:40~飯盛山14:45~岬公園駅前16:20
| 山行期間 | 2018年3月18日 |
|---|---|
| メンバー | SGY, KNS, YDA, FRZ, NKJ, KSU, HYS, ICK |
| 山行地域 | 六甲山 |
| 山行スタイル | ハイキング |

楽しみにしていたBチームの山行が始まりました。
5日前に初めてルームで顔を合わせた、78期生の皆さんとの初山行です。
行き先は六甲山。
行程は阪急芦屋川の駅前に集合して、六甲山の山頂まで登って阪急宝塚駅までのハイキングコースです。
集合は9時になっていたのですが、9時前には全員が集まっており、さすが皆さんのやる気の素晴らしさが伝わってきました。
今回はリーダーの方3名、Bチーム5名の山行になりました。
歩き始めてからしばらくすると、渋滞する事が何回かありました。やはり、六甲山は人気が高いようです。大人から子供、年配のかたまで色んな年齢層の方でいっぱいです。
歩いている時や、休憩している時にリーダーの方からいろんな経験談なども聞くことが出来ました。
六甲山の山頂で記念写真を撮って下山している最中に、たまたまMチームの方々と遭遇するというハプニングにも合いました。
Mチームの方の話によると、今日は、「猿まわし」というトレーニングをしていたとのことでした。
「猿まわし」とは、アイゼンを付けてロープを使ってするトレーニング法らしいです。
冬山に行くときには、欠かせないトレーニングということでした。
自分の今の目標は、冬山に行くことなので、この先どのような山行が出来るのか?また、どのような技術を身に付けることができるのか?今からワクワクしてきました。
Bチームのみなさんとも、いろいろな人と出会うことが出来ました。もうすでに冬山を経験されている方もいましたし、クライミングジムの先生をされている方もいらっしゃいました。
Bチームの中にも、自分よりも上級者のかたが何人もいらっしゃるのでこの先、心強い思いです。
また、山行の帰りには、リーダーの方にBチームの買い物にも付き合って頂きました。
梅田のロッジで山道具について教えて頂きました。
「テント泊に必要な物」「クライミングで必要な道具」など時間をかけて丁寧に説明して下さいました。
リーダーの皆様、Bチームの皆様、これからよろしくお願いいたします。
(FRZ)
<行動記録>
阪急芦屋川駅9:05~大谷茶屋9:30~風吹岩10:25~雨ヶ峠11:15~六甲山最高峰12:30~大谷乗越14:25~塩尾寺15:15~宝塚16:00
| 山行期間 | 2018年1月19日(夜)~21日 |
|---|---|
| メンバー | 21人 |
| 山行地域 | 北アルプス |
| 山行スタイル | 遭難対策訓練 |
今回がBチームにとって、初めての冬の遭難対策訓練になります。五竜のスキー場のキャビンに乗り、しばらくスキー場のなかを進みます。




10時頃、各班に別れて 弱層テスト・ビーコンによる捜索を実施。穴を少し掘るだけで弱層がすぐに分かり、手っ取り早いけれどもいちいち実施していると山に入れないのでケースバイケースだということがわかりました。その後、木の下で1人で入るための半雪洞をほりました。木の近くは暖かく、快適で5分も経たないうちにこちらも簡単に掘ることが出来ました。こういう知識は知ってるのと知らないのとで大きく違うかと思うので、この機会に教わることが出来、よかったです。
実際掘ってみると雪質が色んなものであったり、根っこが出てきたりと説明のように中々上手くいきません。そこで、スノーソーを活用したり、先輩の的確な指示の元でグループで協力しあって作り上げることができました。出口はすきま風が通ると大変なので、ツェルトで塞ぎ、さらにその上からザックで固定しました。雪洞内は風が通らないのですが意外と寒く寝れるかと心配していましたが、寝てしまえば快適そのもので朝まで1度も起きずに寝ることが出来ました。




二日目早朝、装備をつけて集合しある程度高度を稼ぎます。Bチームはそれぞれラッセルしました。少し平になったところで、先輩方に寝ていただき、ツェルト搬送の準備をします。実際今回使った程の人数、道具を確保することは難しいと思うのですが、これほど人ひとりを下ろすのにこれほど大変なのかということを実感しました。




たった2日でしたが多くの学びがあり、経験することができました。これらの知識を使い実践するような状況にはあいたくないですが、いざという時のために繰り返し練習して行ければと思います。貴重な機会を頂き、ありがとうございました。(NGC記)
| 山行期間 | 2018年1月5日夜~7日 |
|---|---|
| メンバー | KNS, SGY, NGS, YMG, ASI, YSZ, HJS, MTD, NGC, TRD, YMK, KWI, SUM |
| 山行地域 | 八ヶ岳 |
| 山行スタイル | 雪山登山 |

1/5(金) 21:00 集合
2018年の山初めということで新年の挨拶もそこそこに、
各々の冬山装備を車に搭載し大阪を出発。
1/6(土) 未明 美濃戸口到着
赤岳山荘の駐車場に到着後すぐにテントを設営。
寒さに耐えながら細かい幕営作業は入山した後の予行演習。
同日 7:30 赤岳山荘出発
各自朝食を簡単に済ませ、ビーコンチェックしていざ出発。
まずは赤岳鉱泉を目指す。

同日 9:00前後 道中
当日は天気にも恵まれ、赤岳鉱泉までの道中は気持ち良いものだった。
多くの人が訪れていることもあり、道も安定していた。


同日 9:30 赤岳鉱泉到着
Bチームは、初めて赤岳鉱泉のアイスキャンディを観る人がほとんどで、
皆アイスクライマーたちに目が釘付けでした。

ここで、トイレ休憩と、幕営装備のデポ。
冬山活動中では限られた飲食のチャンスとのことで、皆行動食をかっこみ
これからのアタックへ向けて補給。
同日 10:00 赤岳鉱泉出発
硫黄岳へアタック開始。気が引き締まります。
同日 12:00 道中
樹林帯を抜け、ピークが見えてきた。
KNSリーダーによると、「そよ風」レベルらしいが、2000メートル越えの冬山体験が初のBチームメンバーたちにとっては、凄まじい強風に感じた人も多かった。

同日 13:00 硫黄岳登頂
途中、体調不良と疲労から登頂せずに中腹で待機の判断をしたメンバーたちもいたものの、
Bチームとしては活動の中で久々の登頂を達成。
このとき、ザックにつけていた温度計は-14度を記録していた。
樹林帯を超えた冬山の気温をまさに肌で感じた。


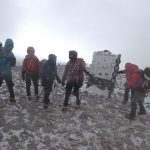
同日 13:00過ぎ 硫黄岳下山
下山開始。とにかく気をつけて下る。
ツェルトをかぶってビバークしている待機メンバーと合流し、赤岳鉱泉まで下る。


同日 14:00 赤岳鉱泉到着
デポした荷物を回収し、小休止を挟みつつ本日の幕営地点である行者小屋へ出発。
同日 15:30 行者小屋到着
すでに多くのテントが設営されていたが、なんとかパーティ分の3張のテントの場所を確保。
幸い幕営場所の気候は安定しており、昨晩と同様に落ちついて設営できた。
しかし、夜中に強風が吹く可能性を考慮して今回は外張りの端に雪を敷き詰めるなど準備を怠らない。
同日 夕方 野営中
テントの中で本日の感想や自由な語らいをしつつ、夕飯。
フリーズドライのカレーとスープが沁みる。嗜好品も夏山に比べて多く摂取し、
いつもよりも水分を補給。翌日の赤岳アタックに向けて就寝。
1/7(日) 6:30 赤岳鉱泉出発
チーズリゾットを朝食にとり、昨日と同様にビーコンチェックをしてからアタック装備で出発。
同日 7:00 道中
行者小屋から赤岳までは開始早々急登が続くが、空は穏やかで、雲ひとつない。
近くの山の頂明るくなってゆき、次第に足元も明るくなっていく。



同日 8:45 硫黄岳登頂
途中、前日の疲労から登頂を断念しSLと共に幕営場所まで引き返す判断をしたメンバーもいたが、CL率いる大部分のメンバーで登頂。
空は晴れているものの、強風は続く。
しばし光景に見とれながらも、帰路へ。


同日 10:00 行者小屋到着
幕営を解除し、赤岳山荘まで帰路へつく。
同日 14:00 赤岳山荘到着
途中道の凍結に足を取られるメンバーもいたが、
無事に全員で下山。

感想
今年初の山行、そして冬合宿ということで、昨年の学びの集大成となりました。
特に11月から開始した冬山に対する座学やアイゼンワーク、歩荷、ラッセルワークを
思い出しながら臨んだ合宿でした。
座学やトレーニングではわからない2000メートルを超える冬山の自然の厳しさなどは
今回の合宿でよく理解できたことと思います。
そして、登った時の達成感や絶景、今回は冬山の厳しさも楽しさもそれぞれ知れたいい機会でした。
<行動記録>
1/6(土)赤岳山荘7:20~赤岳鉱泉9:30~硫黄岳12:55~赤岳鉱泉13:55~行者小屋15:10
1/7(日)行者小屋6:30~赤岳8:30~行者小屋10:00~赤岳山荘12:45
(MTD記)
| 山行期間 | 2017年12月16日夜~17日 |
|---|---|
| メンバー | NGS, SGY, KNS, ASI, SKT, YSZ, HJS, MTD, NGC, TRD, SUM, YMK |
| 山行地域 | 白山山系 |
| 山行スタイル | ラッセワーク |

12/16(土)
21時30分 三国ヶ丘集合
明日の天気予報を持ち寄る。北陸はかなりの降雪の見込み。
テンション上がる人、どんなもんか想像もつかない人、色々な思いを胸にいざ出発。
12/17(日)
2時過ぎに、紆余曲折がありながら白川郷道の駅に到着。
早速テントを張り、実戦を想定して、全ての荷物をテントに持ち込み就寝。
5時30分 起床
1時間で出発とのご指示のもと、テキパキと準備。
朝食は鶏ぞうすいで温まった。
テントから出るまで1時間。
6時50分 道の駅出発
トヨタ自然学校前に移動。地肌は見えない。一面銀世界。
最終準備を行なって7時40分出発。
ちなみにSKDリーダーは、ダンベルを忍ばせて25kgで歩荷ラッセル!
NGSリーダーからの本日の目標
・野谷荘司山ピークを目指す
・進めないときは、12時まで登れるところまで
鶴平新道の入口のある大窪に向かって移動し始めたが、50mで除雪終了。
早速林道ラッセル。トレースがかろうじて残っているので助かる。
500mほど進むと、開けた所となり積雪が増えトレースが消えはじめた。
先頭が深雪ラッセルの洗礼を受けてスピードダウン。交代しながらズンズン進んだ。
が、はて? 鶴平新道入り口が見当たらない。行き過ぎたか? 200mほど戻って、取り付きを探す。と言うより「決める」ことになった。
SGYリーダーによる雪面遊泳の結果、取り付きを「決めて」いただくことができた。
8時10分 標高785m
ここからは雪との格闘が激しさを増すとの見込みで、ここでワカン装着。初装着で手間取る人も。
(何ごとも事前練習しておきましょうね)
8時40分 ワカン装着完了、再出発。
早速登り開始、ノートレースのがっつりラッセル。
もがく。もがく。もがく。少しずつ、少しずつ。少しずつ進む。
約5分格闘するだけで、完全燃焼。そして二番手へと交代。先頭は再充電のため、道を譲り、最後尾へ。これをひたすら繰り返す。
繰り返すうち、分かってきたこと。
・2番手も意外とツライ。(当然、先頭がダントツにツライが)
・先頭と後ろの落差。後ろの方は約10人に踏み固められたトレースなのでフツーに歩ける。
・ラッセルがきついと、どうしてもペースは上がらないので、3番手以降は運動量が少なくなる。冷えに注意する必要性を感じた。
・2~3人のパーティだと、さぞ辛いだろう。
10時45分 標高875m
取り付きから約2時間。初めての休憩。取り付きから約100m登っただけ。樹林帯の中で風もなく、皆思い思いに行動食をほおばる。
約10分の休憩の後、再スタート。
相変わらすの腰までラッセル。気持ちとは裏腹になかなか進まない。
12時00分
行動ストップの設定時間となったが、高度を全然稼いでいない。これだと下りが早いぞと言うことで、もう少し登ることとなった。
ここまでに、各自3~4回は先頭を経験して、要領を掴んできたようだ。
身体を思いっきり傾けて、足を反対側に持ち上げて横から回してくる。そして出来るだけ目の前の立て壁に蹴り混む。
12時20分 965m
そろそろ縦一列ラッセル終了。ここからは、横一列ラッセル。50m先の大きな木まで、本日学んだラッセルテクニックを復習しながら各自がそれぞれのペースでもがく、もがく、もがく。
12時40分
全員が目標地点にたどり着いたところで、二度目の休憩。疲労困憊ヘロヘロの人がチラホラ。
ふと見下ろすと、横一列ラッセルのあとがエライことになっている。まるでゴジラが行水したあとのようだ。
ここでラッセルトレ終了。
13時00分
約20分の休憩の後、下山開始。踏みあとは固く、早い、早い。
13時30分 785m
あっという間に取り付き点まで戻ってきた。
時間も早いので、NGSリーダーからツェルトトレーニングの提案。
強風下で、体温を奪われないように休憩するためのツェルトの使い方を実習した。
ツェルトの中は温かく、訓練を忘れて一瞬くつろいでしまった。
注意点
・ワカン・アイゼン・ピッケルは、外しておく
・強風でツェルトが飛ばされないよう、常に誰かが「しっかりと」ツェルトを掴んでおく
・ツェルトの床の上にザックを載せて重しとし、その上に座る。
14時00分
駐車場に帰着。登頂なきアルピニストの1日は終わった。
今回は近年まれな雪の量だそうで、腰までのラッセルを体感できた我々はラッキー(?)であった。
おまけ
入浴後は、世界遺産「白川郷」を見下ろせる展望台で記念撮影。
さすが世界遺産。絵になるなあ。
(SUM記)
| 山行期間 | 2017年12月3日 |
|---|---|
| メンバー | KNS, SGY, YSZ, HJS, KWI, NGC, TRD, YMK |
| 山行地域 | 屯鶴峯~二上山 |
| 山行スタイル | アイゼン、ボッカ |

昨日は、泉州山岳会の納山祭が開催されたので、いつもよりかなり遅めのスタートでした。
屯鶴峯の駐車場に到着したのは9時過ぎ。
私達Bチーム6名とリーダー、サブリーダーを含む8名は、屯鶴峯の岩場へ到着。
アイゼンを装着し、ザックなしで岩場を歩く。
フラットフィッティングを意識しながら、ゆっくり一歩ずつ。
岩場を登ったり降りたり、とても天気が良いので、直ぐに汗だくになった。
膝を曲げ、重心の置き方を意識しながら歩くのだが、少し幅の狭い箇所になると、どういう風に足を置いたら良いか迷い、ふらつく事も度々あった。
しかし、11月の蓬莱峡でのアイゼントレーニング、木曾駒の雪山を経て、今回でアイゼンを装着して歩くのは3回目。
前回より少しはできたかなと思いながらトレーニングは11時5分に終了した。
今度は場所を移動し、猿回しのトレーニングを開始。
かなり急な岩場にザイルを張り、アイゼンとハーネス装着して、登ったり降りたりを5本行った。
ここでは真っ直ぐ下を向いて降りるのが目的。
真っ直ぐ下を向いて降りるためには膝を曲げ太ももの筋肉を使うので、私の一番苦手なトレーニングです。
蓬莱峡では何度もずり落ちました。上手な人はさっさと降りていきます。
私は前回ほどずり落ちませんでしたが、かなりゆっくりめで降りました。
膝を深めに曲げると怖さが少し軽減する事を理解し、場所によってはほとんど座りそうなくらい膝を曲げて降りました。
12時55分に猿回しを終了した。
休憩後、歩荷のための石をザックに入れる。
私は自信がないので、今回は20.6kg。T氏は28kgにすると宣言。
13時45分に登り始めた。20.6kgのザックはかなり重い。
地面にあるザックを背負うのもなかなかできず、情けないが一人であげる事ができなかった。
膝にザックを乗せた後、背負うまでが何度やっても振られてしまった。
登りは階段の高さがきつく直ぐに汗だくとなった。
今回は、雪山の事を考えてなるべく汗が出ない服装と思い、夏用の長袖を着ていたが、失敗の様だった。
服装を改めて検討する課題ができた。28kgのT氏はゆっくりでしたが、他のメンバーは先ほどまでのトレーニングはなかったかの様に軽く登って行った。
二上山までは階段が多くまたアップダウンもあり、私は今回もゆっくりしか進めなかった。
15時過ぎに展望台へ到着。展望台からの景色はとても美しくしばし休憩。
そこから少し行った雌岳山頂へは15時45分に到着した。
暗くならない内に駐車場へ到着できたらと、直ぐに下山。
途中鉄塔の所では、夕日と赤く色づいた紅葉の山々がとても美しく景色を楽しんだ。
徐々に暗くなっていった。
途中かなり薄暗かったがなんとかライトなしで下山。
17時5分歩荷終了の合図。
直ぐに石を捨てる。とても軽くなったザックを背負い17時25分に駐車場に到着。
トレーニングの必要性を強く感じながら、今日の山行は終了した。
天気も良く暖かくとても良い山行でした。リーダー、サブリーダーの皆さま本当にありがとうございました。
<行動記録>
アイゼンワーク 9:30~11:05
猿回し 11:00~12:55
歩荷 駐車場13:30~ダイトレ入口13:45~二上山休憩所15:10~二上山雄山山頂15:45~ダイトレ入口17:05~駐車場17:25
(KWI記)
| 山行期間 | 2017年11月24日夜~26日 |
|---|---|
| メンバー | SGY, NGS, KNS, YMG, YSZ, HJS, KWI, NGC, TRD |
| 山行地域 | 中央アルプス |
| 山行スタイル | プレ冬山 |

プレ冬山山行として、木曽駒ヶ岳へ行ってきました。
もとは別山へ行く予定でしたが、白山周辺は積雪により車両通行規制がかかっていると判明し、木曽駒ヶ岳へと変更になりました。
今回は上松Aコースにて、8合目をベースキャンプとし、木曽駒ヶ岳を目指す計画でした。
道の駅で仮眠をとり、8時前に駐車場を出発。
0.5合目ごとに立つ標識を目印にして登っていきます。久しぶりに身につけた冬山装備でしたが、重ね着やザックの重さで身動きが取りにくく、やはり冬山は体力がより必要であることを感じました。
6合目で休憩中、下ってきた先行の日帰りパーティーと出会い、「7合目半手前で折り返してきました。今日中に8合目まで行くならかなり頑張らないといけないですね」と声をかけていただきました。
この時点ですでに14時をまわっており、またそれまではこの先行パーティーのトレースを目印に登ってきたため、その先トレースがなくなると、更に時間がかかりそう・・・と不安になりました。
どんどん雪が深くなるためツボ足になることも多く、キックステップを意識して登るようにしました。
7合目半手前にて16時近くになったため、テン場となりそうな場所を探し、山道の側にテントを張りました。
雪山で、またテン場でない場所へのテント設営は初めてでしたが、整地やペグの埋め込み等に時間がかかり、予想以上に大変でした。
日は落ちかけると早く、テント設営後は真っ暗になり、寒さも厳しくなりました。
テントに入り、雪袋に詰めておいた雪を使って夕食、朝食用の水を約5~6L作りました。
雪が溶けるまでは案外時間がかかるため、水作りにも予想以上の時間を要しました。その後、夕食でお腹をいっぱいにして就寝。
翌日は4時に起床し、ワカンを装着して6時過ぎに出発。ワカンを着けると足の沈みがずいぶん軽減され、昨日より歩きやすくなりました。
途中、先行パーティーのトレースがなくなりラッセルが必要となってからは、進むスピードが随分と落ちました。その後、後から来たパーティーとラッセルを交代しながら進みました。
森林限界を超えてからは更に雪が深くなり、こんなに深い雪の中を歩くことは初めてだったので、一歩一歩が精一杯でした。
私は最後の15分ほど先頭ラッセルをさせてもらいました。
先頭ラッセルは体力的にはとても大変でしたが、誰も踏んでいない新雪にトレースをつけていくことは、なんとも気持ちが良く最高の気分でした!また天気が良かったため、周りの景色や、風に舞ってキラキラしていた雪がとても綺麗でした。
ただ、積雪のある稜線上のコースの取り方が難しく、踏み抜いて滑落してしまうのではないかという怖さがありました。
今回は膝までのラッセルでしたが、これが胸まである場合は、また一段と難しいのではないかと思いました。
帰りの時間を考えて8合目半手前にて引き返し、15時頃駐車場へ到着しました。
今回は、冬山での歩きや装備の使い方、テント泊、ラッセルと様々な経験ができ、プレ冬山としてとても充実した山行でした。
課題もたくさんありますが、これからの冬山山行がとても楽しみです。
リーダーをはじめ、Mチームの方々には大変お世話になりました。
ありがとうございました。
<行動記録>
11/25 砂防公園7:20~敬神の滝小屋8:00~3合目9:00~4合目9:45~金懸小屋11:15~5合目12:45~6合目13:30~7合目15:05~テント設営16:30
11/26 テント場6:20~8合目8:00~2680mのピーク(木曽前岳手前)9:05~テント場10:35~金懸小屋13:40~敬神の滝小屋15:45~砂防公園16:10
(HJS記)
| 山行期間 | 2017年11月11日(夜)~12日 |
|---|---|
| メンバー | SGY, NGS, KNS, YSZ, KWI, MTD, NGC, TRD, YMK, SUM |
| 山行地域 | 六甲 |
| 山行スタイル | アイゼンワーク、歩荷 |

山トレーニングが始まります。
この日に向けて、お金も時間もかけて、装備を揃えて来ました。
宝塚駅に集合し、20時20分の最終バスで、蓬莱峡へ。
5月のクライミング練習以来です。
あれから、半年。それぞれ、経験を重ねてきました。
少しは成長できているでしょうか。
テントを張り、小宴。
少し雨が降ってきたので、22時には就寝しました。
6時に起床、朝食後、まずはアイゼントレーニング。
事前の説明の時に、アイゼンを付ける練習をしておくようにと言われていましたが、やっぱり装着するのに時間がかかりました。
カッパドキアを彷彿とさせる岩山の中、お天気よく、紅葉もいい感じです。
足はフラットに置くこと、足を置いたら、迷わず信用して体重をかければアイゼンがしっかりきくことを、教わります。
教えられた通り、できたり、できなかったり。
身体で感じます。
次は猿回し。角度が急な一枚岩の壁にロープを張って、フリクションヒッチで確保しながら、
岩場を登ったり下りたり、三往復。
私たちの新しいアイゼンはよく効くから大丈夫と言われても、やっぱり体重をかけきれません。
下から見るとそう急で無いように見える斜面でも上から見ると、かなり急です。
1回目は怖くて仕方ありせんでしたが、回数を重ねるごとに少しずつ慣れてきました。
テントを撤収し、歩荷です。
荷物に石を詰め込み、20 kg以上にして、宝塚まで歩きます。
藪漕ぎ状態の山中を歩きました。
渡渉もあり、足場が悪いところもありましたが、みんな頑張りました。
石を降ろして、達成感とともに、気分も軽く宝塚駅まで。
今日は、先輩方がアイゼンつけても難なく歩く姿に、これからの目標が見えてきました。
これからの冬山ステージ、よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
<行動記録>
アイゼンワーク 7:30~9:30
猿回し 9:30~12:50
歩荷 蓬莱峡12:50~大谷乗越15:50~塩尾寺17:00~宝塚17:50
(YMK記)
| 山行期間 | 2017年10月13日(金)夜~15日(日 |
|---|---|
| 山行地域 | 岡山県『備中』 |
| 山行スタイル | フリークライミングおよび読図・天気図学習会 |

第4ステージのフリークライミング山行
今回のクライミング山行は、岡山県高梁市備中へフリークライミング山行へ行ってきました。
10月13日(金)PM9:00「三国ヶ丘駅」へ集合して、諸先輩方の車へ乗せていただき岡山県備中へ向かいます。
西日本最大級のクライミングゲレンデでのフリークライミングができることに胸を躍らせながら期待します。
約3時間半で目的地の用瀬小屋へ到着です!
辺りは真っ暗です。ヘッドライトを装着し、まずは、テントの設営を行い就寝。
就寝中、雨が降り朝からクライミングに恐怖を感じながらAM5:00起床。
山岳会で山行の朝は忙しい・・・
テント撤収・各自のシュラフ、マット等の持ち物の片付けをササッと済ませ各自用意した朝食を食べる。
AM6:15頃より小雨混じりの中、用瀬小屋上部にある岩場「キャンプサイド」へ向かう。
岩場を見たとたん「ここ登るの?」とレベルの高い感じになりました。
諸先輩方がトップロープを各岩場にセッティングしてくれます。
先輩方のロープをセッティングしてる姿を拝見しすごいと改めてクライミングの魅力を感じさせていただきました。
今回登攀するルートは①ピーチ味(5.9)、②ドゥーヴ(5.10c)、③ワンストップ(5.10b)、④イエローブック(5.9)どれも簡単に登れるルートではありません。
覚悟を決めてトップロープで『ピーチ味』に挑戦・・・何度も敗退しながらも「こんなとこ登るんやぁ~」と思いながら何とか登ることができました。
続いて『イエローブック』、『ワンストップ』へ挑戦しましたが見事敗退・・・
Bチームの皆様も何度も敗退しながらも挑戦していきます。
お昼からは『長屋坂』へ移動。
こちらのルートは①ザク(5.9)、②プラナン(5.9)などを登りました。
一番やさしいとされる『ザク』を選択しトップローで挑戦します。
途中までもかなりの時間を要しながら登りましたが、核心部からどうにもこうにも登れません・・・あえなく敗退しました。
他のルートは、自分のレベルでは歯が立たないことがわかりました。
もっと技術・経験を積み再度挑戦したいと思います。
15:00頃クライミング終了し本日お世話になる『クライマーズハウス木の村』へ
本日の夜の晩餐はBBQ食料買い出しチームと準備チームに分かれ晩餐の準備にとりかかります。
Mチームの諸先輩方とも懇親を深め楽しい晩餐となりました。
初日は22:00頃終了(就寝)
二日目は雨の為、クライマーズハウス『木の村』で屋内授業を受けさせていただきました。
①読図(地図読み)
25000分の1の地図にて谷筋・尾根筋等を理解する重要性。冬山では目印がなくなるので読図できないと遭難する可能性が高い事など色々とアドバイスを含め教えていただきました。
②天気図の書き方
山での天候状態を把握する手段で非常に重要
ラジオを聴きながら内容を天気図用紙に書いていくことを実際に音声を聴きながらの作業を体験させていただきました。
天気図マークもほとんど知らない状態での天気図記入・・・ほんと難しかったです・・・ほぼちんぷんかんぷんでしたが、なんとなく理解はできた感じです。
読図と天気図に関してはこれから頑張って出来るように勉強していきます。
13:00頃室内講習修了。
片付け等を行い帰阪しました。
今回の山行では、自身の未熟さを痛感できる良い二日間となりました。
SKDリーダー本当に色々とお世話になりありがとうございました。
厳しさの中にたくさんのやさしさを頂き、本当にありがとうございました。
今回の山行にご尽力いただきましたMチームの皆様お疲れ様でした。
今回参加されたBチームの皆様、お疲れ様です。
(TRD記)
リーダー後記
今回は困難なルートを登る体験をしていただきました。
一番優しいと言われるルートでもかなりトレーニングを行わないと登れないことを体感していただけたと思います。
今回備中で登っていただいたルートは備中の中で一番優しいルートになります。備中に来る人はもっと高難易度のルートを目的に来られる方々がほとんどです。
近郊のゲレンデで実力を高めて、今後備中で色々なルートに挑戦していただければと思います。
二日目は完全に雨だったので、ルームでみっちりできない講習をしっかり受けていただきました。
山に入る為に絶対できなければいけない「読図」と「天気図記入」について、ほぼ半日かけて学習していただきました。
まだまだ伝えきれていない部分はたくさんありますが、今回学習したことをご自宅等で自主学習していただいて、実際の山中で試していただきたいと思います。
自然の山はいつも穏やかな顔をみせてはくれません。急に天候が荒れたりしますので、今回の学習内容は天気を事前に予想して、危険を回避することと、地図を見て確実に自分のルートを外さないこと。
これは山から安全に下山する為に必ず必要なことです。今回の学習だけでなく、自主的に学習してたくさん知識をもって山行に望んでいただきたいと思います。
山行は安全に下山することが一番だと思います。今後も安全に楽しく、そして厳しい山行が出来るように楽しみながら経験を積んでいただきたいと思います。