アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ! 大阪府山岳連盟所属

| 山行期間 | 椿岩:久しぶりのフリークライミング |
|---|---|
| メンバー | TYK,MRJ,KRA,INO |
| 山行地域 | 椿岩 |
| 山行スタイル | フリークライミング |
今回は76期のメンバー3人と、75期のメンバー1人で椿岩にフリークライミングに行きました。
TYKさんが、「僕、遭難対策訓練が1泊2日だと思って土曜日も空けてたんですけど、日帰りになったから土曜日も空いているんですよね。。。」という、つぶやきから、「じゃあ外岩にフリークライミングに行きますか?」ということから、同期のMRJさんを誘い、私が一人で不安だったため、75期で職場の同僚のKRAさんを捕まえて、外岩に行くことになりました。
とりあえず近場で椿岩。
私は椿岩に行ったことがなかったので、楽しみ。わくわく。
しかも車を出してくれたのはTYKさん。なんと納車して1ヶ月もたたない新車!!

ヒルがいるとの情報でしたが、特に問題なく岩場に到着。
まずはKRAさんが5.9のアスレチッククラブをマスターでかけます。
その後にMRJさんがトライするも確信部分を抜けれず。。。

次にまたKRAさんが、5.9のマタニティをマスターで登り、今度はトップロープ状態にしてくれます。そしてTYKさんのトライ。なかなかうまく行かず、なんども挑戦しますがねけれません。

KRAさんと私は5.10bのマリエンタールをさわります。KRAさんはテンションかけながらもムーブを解決しますが、私は、ピンから左にランアウトしている状態が怖くて怖くて手が出ません。結局KRAさんはRPされ、私は上まで抜けれずでした。
MRJさんは何度もアスレチッククラブをさわり、最終RPされていました。さすが!
TYKさんもマタニティを何度も挑戦しますが、ほとんどクライミングをしたことがないのでトップアウトできず。。。「修行つんで、必ずリベンジします!」といき込んでおりました。
KRAさんは5.11b/cのケイブマンに挑戦します。まずは、ゆっくりオブザベして。。。

それから登ります。テンテンながらも、さすが、上まで抜けてしまいます。

私は5.10cの燃えよドラゴンに挑戦。なんとか上まで抜けるものの、ほぼ1時間は粘っていたでしょうか。。。KRAさんビレイすみませんでした。今回はRPできなかったので、次回の宿題です。
気をとりなおして、5.9のアスレチッククラブでダウン。快適。

楽しかったなー!! やっぱり外岩は楽しいな。フリーは楽しいな。
と充実した1日を過ごしました。
またみんなでリベンジに来ましょう!
記:INO
| 山行期間 | 5/20夜ー21日 |
|---|---|
| メンバー | Bチーム11名、Mチーム8名 |
| 山行地域 | 蓬莱峡 |
| 山行スタイル | 育成トレーニング |

(メンバー)
DTE(CL) HND(SL) YMG(SL) ABE UET TKD ASI WDZ
Bチーム : YSZ KWI FJS YMU YMK HRZ KTM MTD SMA TRD NGC
77期初岩登り山行:蓬莱峡
77期としては初の岩登り山行となります。
最高の天気に恵まれ最高の山行の始まりです。
前泊にて現地へ乗り込み翌、早朝より岩登りの基礎を学びます。
5月20日PM8:10分阪急宝塚駅の阪急バス停2番乗り口集合。
Bチーム8名Mチーム諸先輩方7名の15名で現地へ向かいます。
(翌朝、現地集合の方4名)総勢19名。
PM8:20バスに乗り込み座頭谷停留所で下車後、目的地まで歩いて行きます。
バスに乗り込む時は、まだ明るかったのですが停留所へ着く頃には暗闇と化しています。
ここでヘッデンを装着しテント場まで歩いて行きます。
山道を歩き小さな川を渡り本日の寝床(テント場)へ到着!!
到着したらまずテントの設営を行います。6人用テント3張り設営します。
諸先輩方に設営の仕方を教わりながら設営します。無事3張り設営完了!!
PM9時30分頃より懇親会を行いしばし歓談し楽しい時間を過ごさせて頂きました。
約1時間程度、歓談後それぞれのテントに帰り就寝。
初、岩登りという事で期待と興奮もあり、あまりよく寝れないまま朝を迎える事となる。
AM6時起床
今回、私とNさんで、初朝食担当をさせて頂きました。(食材を用意させていただいただけですが・・・)
メニュー
ワカメスープ・ウィンナー・バターロール・ハムロール・しゃぶ餅
各自、嗜好品コーヒー等を頂きます。
朝食終了後、テントを撤収し本日の岩登りの準備を行います。

AM7時10分ハーネス・ヘルメット・PAS等を身につけ集合
本日の目的の岩がある所へ移動
4チームに分かれて基本的なロープワーク・動作等々を教えて頂きます。
AM8時~10時
樹林帯にフィックスロープを張っていただき、フィックスロープの通過(フリクションノットで通過・
カラビナ通過の練習をしながら教えて頂きました。

AM10時~12時
懸垂下降の練習
実際にロープを使った状態でロープの結束方法・確保器の使い方・フリクションヒッチによるバックアップの練習が出来たので非常にわかりやすかったです。
PM12時~3時
いよいよ実際の岩山(小屏風)に取り付き本格的に練習が始まります。
午前中に練習したフリクションノットをフィックスロープへセットしフィクスロープの通過・セルフビレイの取り方等を丁寧に教えて頂きました。


懸垂のシステム講習のあと
今回のメイン懸垂下降いよいよスタート。

実際の岩では岩が飛び出していて下が見えない様な状態の所から降りるのは、少し緊張しましたが
安全確保を確実にしているので楽しみながら懸垂下降できました。


まだまだやりたい所でしたが、撤収の時間です。
3時38分のバスに乗るので岩に設置したロープカラビナ類の撤去片付けを済ましバス停へ向かいます。
座頭谷バス停から阪急宝塚駅に到着し解散となりました。
今回の山行リーダーをして頂いたDさんHさんYさんありがとうございました。
又、色々とフォローして頂いた先輩方、共同装備を分担して持っていただいたBチームの皆様ありがとうございました。
おかげさまで怪我無く楽しい山行になりました本当にありがとうございました。
MチームBチーム参加された皆様お疲れ様でした。
今回、学んだ事を次回に活かせる様にBチームの皆様復習しましょう。
TRD記
| 山行期間 | 5/16~5/17 |
|---|---|
| メンバー | TGA TTH KSI |
| 山行地域 | 御在所岳前尾根 |
| 山行スタイル | 岩登り |
平日山行で御在所岳の前尾根に行ってきました。
16日、22:30三国ヶ丘出発。菰野市・道の駅ふるさと館にて駐車、そこでテントを張って仮眠。
5時起床、朝食後、5時45分には登山口に駐車、荷分けをして歩き出しました。
天気は晴れ。爽やかな空気が気持ちいいスタートです。

DSC_0172
6時23分、藤内小屋着、水を確保します。平日で宿泊客もいないのか、誰もいません。そこから約30分ほどでP7の取り付きに到着。少し緊張しながらリーダーの指示に従い準備を始めます。
TTHさんは2度目ですが、私は去年育成の前半クライミングステージ以来の岩でした。後半のステージでマルチピッチが出来なかったので今回がまったく初めてのマルチピッチです。絶対行くぞと願ってた前尾根。ロープワーク、初期動作の手順、確保、予習してきました。関連動画も何度も見て足掛かりの手順等、イメトレはばっちり・・?不安3期待7でいっぱいです。
リーダーからここで色々レクチャーを受けました。中でも人の加重がいかに衝撃を与えるか、リーダーがちょっと落ちた風にしただけで軽く私の身体は飛びます(ここではまだセルフビレイを取っていません)。自身の体で味わうことで怪我をしないための知識や準備がいかに大事か、セルフビレイをとる場所、距離の意味を身をもって知ることが出来ました。
気が引き締まったところで7時45分、いよいよP7からスタートです。私とTTHさんのロープをアンザイレンしたリーダーが上っていきます。私は2番目に登ることになりました。行けそうで行けない、みたいな壁。とにかく少しずつ登りますが、上手く足が掛けれないところになると、指先の感覚がすぐさま無くなります。下からTさんの声で進むも必死のクリア。ここで不安7期待3。

P6を過ぎた頃からでしょうか。岩が楽しめるようになってきました。
風景も遠く見渡せ、暑くもなく、寒くもなく、出会う人も1人の方や、2人組くらいなので私が遅くてもプレッシャーを感じず岩に集中できます。高度感に震えるのでは、と思いましたが全然楽しかったです。

DSC_0176
P3まで来ると、クラックと言うほどかわかりませんが、細い割れ目を登っていくのに両足を突っ込みました。い、痛い・・。痛いけどこれしか登れそうにない。「Kさーん、ここが最後の難所だから」。片方づつ休憩し、痛みを逃しながらなんとか登ることが出来ました。ここで15時。終了です。
ヤグラを目の前にしつつですが、それでもここまで登れた事に感謝です。
ギアを片付け後、3人ともまだ山頂の一等三角点に行ったことが無いと言うので行くことになりました。伊勢湾、琵琶湖と同時に見渡せる景色はなかなか絶景です。
後は裏道で下山。希望荘で汗を流し、美味しい和食のお店で食べて帰阪しました。
リーダーのTGAさん、私のリクエストに賛同してくれたTTHさん、お疲れ様でした。
そしてありがとうございました。

| 山行期間 | 2017年5月6日(夜)~7日 |
|---|---|
| メンバー | OSM、TTH |
| 山行地域 | 比良山系 |
| 山行スタイル | 沢登り |
Bチームを卒業したばかりのTTHさんをつれて、前から初心者を連れて行けそうな沢の候補として、ヘク谷に行ってきました。印象としては、初心者を連れて行くにはもう少し簡単な沢があるように思いました。水も冷たく、腰から上に入るには勇気がいりました。
入渓は、国道から橋をくぐってすぐに数台とめれるところがあり、そこからできました。



苔が多く、フェルト向きの沢だと思います。








なかなかいい沢でした。登攀具などは持って行ったほうがいいと思います。
6:15出発→7:15 500m辺り→7:30 540m辺り→9:30 750m→10:47 1000m辺り→11:12小女郎ヶ池→12:30林道
計画ルート:
5/4 源次郎尾根~剱岳~長次郎谷
5/5 長次郎谷~剱岳~早月小屋
5/6 早月小屋~馬場島
CL:ABe メンバー:tkd、wdz
5月3日 (立山~長次郎谷出会)
。
Mチーム2年目の春。
いよいよ入会時の目標であった剱岳に向かいます。しかも残雪期。どきどきわくわくです

初剱。
思っていたよりも小さいか?

でもやっぱり格好ええです
別山尾根から頂上まで綺麗に見えてます

来たぞーって感じでしょうか
5月4日(源次郎尾根~山頂、、、予定)

前日に調査しておいた取付き部です。

尾根へ
岩との間はどこも雪がとけていて大きな穴が開いており踏み抜くことも、、、
草付き部ではかなりハイマツを引っ張り、踏みつけながらの急登
 抜けてもかなりの雪面の急登時間がかかるが仕方なくロープをだす。
抜けてもかなりの雪面の急登時間がかかるが仕方なくロープをだす。
この時点ですでに敗退色濃厚を予感
時間はもう7時を回っているのに一峰さえも見えず

稜線に出るとこんな感じ
細いですが、それより雪が緩いのが恐ろしいです。
(、、、、、、、、やはりの予想通りの敗退、、、)
上の写真の少し先は雪庇が張り出しており、確保支点もなく一峰を上っているパーティーを眺めながらあっさり敗退。
(結局一峰ピークまで3時間位かかっている様子)
取付くことさえ出来なかった、、、時間は8時30分。 早っ

というわけでさっさっとテント場にご帰還。
天気も良く、時間もたっぷり、、、
洗濯日和です。
(5月5日 長次郎谷~剱岳山頂~早月小屋)
前日の雪の具合と疲れ具合、全装備を持っての行動ということで本日は1時起きの3時出発。
真夜中にヘッドランプをつけての行動ということで途中ルートをミスったりするが、とりあえず順調に日の出を迎えるが身体が重いし、早朝?出発のかいもなくやはり雪はかなり緩くプチラッセル。

しかし綺麗
絵の様である。
写真家の山への愛があふれてるね~

昨日登った一峰取りつき手前の0峰?
こうやって見ると小さい
というか、一峰でかい!!

長次郎谷でかっ!!

ともあれ無事登頂。
ずっと晴れてたのに
ピークはガスガス。

早月尾根への下り看板


はい。早月尾根からの眺めです
いまはスッキリ晴れてます。
ちぇ
ライチョウです。
今回山行では9羽のライチョウさんを確認しました。
しかしこやつら登るの早いな。
急な雪面もたたたたたっ~
って、、、飛べよ!!

早月小屋が見えてきました
核心となる箇所もほぼ通り過ぎ少し尾根も広くなってきました

本来は小屋で一泊の予定でしたが、今晩からの天気が思わしくないため下山します。
雲の活動も活発で出来たり消えたりを繰り返しているようです。
 はい。馬場島到着です。
はい。馬場島到着です。
全員けがなく無事下山です。
今回の山行では源次郎尾根からの登頂をメインの計画にしていたが思っていたよりも雪が緩く、天気も7時には暑くてかなり危険な状態であった。実際このGWではかなりの遭難事故もあり残念ながら亡くなった方もいたようです。我々もルートミスなく源次郎尾根に取付いていたらおそらく時間切れによるビバークを余儀なくさせられるような状態で結果的にはよかった、助かったと感じられた。しかしルートミスはルートミス、偵察を含めメンバー各々の調査不足は否めなくこれにより危険な状態に陥る可能性もあることを痛感した。
(wooodz)
| 山行期間 | 2017年5月4日夜~6日 |
|---|---|
| メンバー | SGY(CL), MSD(SL), TYK(SL), MEM, TKH, YMS, KSH, INO, SOT, MRJ, TNK |
| 山行地域 | 剱岳 |
| 山行スタイル | 春山登山 |
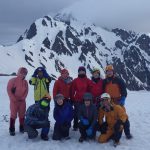
2017年春合宿、SGY・MSDパーティーは主に67期の新Mチームメンバーとともに、剱沢をBCとして長次郎谷より剱岳を目指しました。しかし、いやまたこれが…
5月5日 快晴
2:30立山駅駐車場着、仮眠。5:30起床、7:00過には切符売り場の行列に並ぶも、物凄い混雑で約2時間を駅構内で過ごす。渉外のYMSさんはじめ、SGYリーダー、INOさん、長時間を行列に並んで下さりありがとうございました。
9:10の臨時直通バスにようやく乗車し、室堂へ。室堂でも観光客や登山者、山スキーの人々でごった返し。後で聞くと、子どもの日ということで子どものケーブル料金が無料だったとのこと。どおりで、家族連れも多かった印象。
10:25 室堂発。雷鳥沢まで重に下りなのに、強い日差しに意外な高気温で汗だく。すれ違う登山者らも半そでで真っ赤に日焼けしている方も。このため、雷鳥沢でカッパ上下を脱ぐメンバーも。「温度差±10℃は自分で調節できる」SGYリーダーはカッパズボンをそのまま、再出発。ここから別山乗越まで登り。
日も高くなり、気温も高いため。雪がやや湿り気が多い。春山シーズンということもあり、しっかり沢山のトレースがあるため、この上を選びながら歩くことで、軟弱者の私としては体力の消耗を最小限に抑えようとした。が、息が上がる~!でも、苦しい登りであっても、次々に現れる雷鳥に癒される。そこでも恋愛劇が…一羽のオスがメスに求愛、振られるや否や、次のメスに乗り換えてまた振られた。「そんな尻軽男、要らんわ~って言われたんや」とSOTさん。
14:00剱御前小屋でトイレを借り、小休止。小屋や営業中、結構な賑わいである。ここからテン場までの下りは、テントが見えているだけに足が軽く、壮大な剱を見ながら、「八ッ峰、長次郎、源次郎」なんて言いながら歩く。14:40テン場着、テント設営に全員がスコップを持って取り掛かるも、雲の合間に見える山頂が気がかり。設営後は撮影に余念がない。
5人用テント、6人用テントに夫々わかれて幕営。夕食はシチューのご馳走!
5月6日 雨
予報によると本日は雨。雨が降れば長次郎は雪崩の巣になる、ということで、2:30起床4:00まだ暗い中を出発。ところが20分程も歩いていないところに、山岳警察に呼び止められた。「どちらに行かれますか?」「今日は雨が降るって知っていますか?」「今、遭難者の救助に徹夜でかかっていたんです。長次郎はブロック雪崩が置きかけていて、雨が降ったらどうなるかわかりますよね」等々、手厳しい。我々は引き返し、4:40剱沢キャンプ場着、撤収にかかった。そして全員で記念撮影後に剱岳を後にした。
さほど進まぬうち、雨が降り出し、我々は濡れながら別山乗越まで登り返し、稜線の突風にビビリながら数分下ったところで風が止む。この稜線沿いとの差に、山の厳しさを学んだ。
室堂に近づく程に、雨風の中傘も差せずに歩く観光客とすれ違いながら、今回の登山を終えた。
~~~~~~~~~
近辺の山でのトレーニング、木曽駒での雪上訓練や唐松での稜線歩きを経ての春合宿。悪天候と県警のため、取付も偵察することなくベースキャンプから程なく帰還となったが、雨の降らないうちにBCを撤収でき、濡れ鼠のまま1泊することもなく、無事に帰ることができた。春の雪山の雪崩の恐ろしさ、気温により雪であったり雨であったり、稜線での強風に足がよろめいたり、新雪・グサグサ雪と、状況による変化を経験して行けることは非常に有意義であった。
行動記録
20170505
9:10 立山駅発-10:10 室堂着(直通バス)
10:25 室堂発
11:20 雷鳥沢キャンプ場 衣類調節
14:00 剱御前小屋着
14:40 剱沢キャンプ場着
20170506
2:30 起床
4:00 剱沢キャンプ場発(アタック装備)
4:40 剱沢キャンプ場着、撤収
5:20 剱沢キャンプ場発
6:10 雷鳥フュッテ
8:30 室堂着
| 山行期間 | 2017年4月28日夜~30日 |
|---|---|
| メンバー | SGY(CL), MSD(SL), INO(SL), MEM, TKH, SOT, MRJ, TNK, TCH |
| 山行地域 | 北アルプス |
| 山行スタイル | 春山登山 |

5月GW、剱岳長次郎谷ルート挑戦に向けての2ヶ月にわたるトレーニングの最終回として、
唐松岳登頂とテント指定地以外での幕営訓練を行った。
4/28(金)
梅田集合組は、予定より20分ほど遅れて出発。三国ヶ丘出発組と多賀SAで合流。順調に八方駐車場へ到着。
3:30より3時間仮眠。
4/29(土)
八方駐車場から山麓駅まで約10分。
その途中で自分がアウター手袋を家に忘れてしまったことに気付く!バタバタさせてしまった。
INOさんが予備を貸してくださることで対応。
猛省です。
ゴンドラは荷物15kg超の場合、荷物代有料となる。
係員に計量を指示され、4名が撃沈。
4つ分の荷物料を追加支払い。
ゴンドラとリフト2本を乗り継ぎ、一気に標高1,830mの世界へ。
雲が広がっているものの、南の遠見尾根はほぼ見通せるまずまずの天候。
予想より雪が少なく、雪だったり土だったりの道を順調にすすむ。
あっという間に幕営予定地に到着し(この時点で、そこは上樺と思い込んでいたが、実際には下樺)、
アタック装備のみを持ち、さらに上を目指す。
相変わらず雲はあるものの、たま~に青空が見えたり、ガスがとれて白馬三山の稜線が見えたりと、
景色を楽しみながらすすむ。
夏道コースタイムより短い時間で、頂上山荘へ到着。
ここまで快調にきたが、稜線にあがると風が強い上に、急に雪が降り出し、みるみる吹雪の様相となってきた。
急いで山頂を目指す。
頂上までわずか20分の距離、視界があればあっという間と感じるはずの道が、風雪で見えにくくなり、
ちょっと気を抜くと前の人を見失いそうになり、必死でついていく。
そして、とうとう登頂!全員が登頂するのを待って、吹雪の中記念撮影。
その間に、雷まで鳴り出した。
会長の「長居は無用や!」の号令でさっさと下山開始!急ぎ頂上小屋付近まで下り、体制を整え直して、さらに下山。
登りではなんてことなかったトラバースが、下りでは雪を踏み抜かないよう大変気を使ったりと、
やはり感じ方が違うと実感。
雷が頭の上で鳴り続ける中、急いで幕営地まで戻った。
テント設営のための土方作業開始。
6人用テントと4人用テントの2張り分の設営は大変だ!と思っていたが、
9人の力を合わせて、全員でスコップをふるい、ブロックを積み上げ、雪をならし、
1時間程度で素晴らしい2世帯住宅用スペースができあがった。
作業している間に、雷も遠くへ行き一安心。
風はとても強かったが、ブロックがしっかりさえぎり、不安なくそれぞれのテントでおしゃべりと夕食を楽しみ、
20:00頃就寝。
4/30(日)
外は快晴!遠見尾根も白馬三山の稜線もすべて見通せる。
「今日が登頂日だったら・・・」との思いもあるものの、風雪と雷の中登頂した経験は大切、と思い直す。
今日は下山のみで時間に余裕があったので、テント撤収して出発前に、会長が弱層テストをやってくださる。
こういう一つ一つが、本当に勉強になる。
斜面の状態も観察し、疑問質問に答えていただいた。
ぴかぴかの快晴の中、下山開始。そしてわずか30分でリフト乗り場に到着。
リフトとゴンドラを乗り継いで、町までらくらく下山した。
次はいよいよ本番の剱岳、どうか全員無事に怪我無く登頂できますように。
<行動時間>
4/29(土)
7:40八方第3駐車場
7:55八方尾根スキー場山麓駅(ゴンドラ&リフト)
8:35八方池山荘
8:55八方山ケルン
9:25八方池
10:00下ノ樺
11:55唐松岳頂上山荘
12:30唐松岳
12:55唐松岳頂上山荘
14:30下ノ樺(幕営地)
4/30(日)
7:30下ノ樺(幕営地)
8:00八方池山荘
8:40八方尾根スキー場山麓駅(リフト&ゴンドラ)
| 山行期間 | 2017年4月14日夜~16日 |
|---|---|
| メンバー | SGY(CL), MSD(SL), TYK(SL), TKH, YMS, KSH, TCH, INO, SOT, TNK |
| 山行地域 | 中央アルプス |
| 山行スタイル | 春山登山、雪上訓練 |

春合宿で剣岳を目指すための雪訓を兼ねた、中央アルプス。千畳敷カールでの雪訓と、2日目は木曽駒ケ岳を目指しました。
4月14日
大阪もしくは三国ヶ丘駅21時発で、駒ヶ根を目指しました。
4月15日
4月の例会メンバーとともに、菅の台バスセンターからバス、ロープウェイに乗り込みました。17名の大所帯!登山客や一般客以外にもスキーヤーやボーダーもいました。
例会メンバーと別れてカールでの雪上訓練。まずは雪上でのキックステップや、トラバース、滑落停止等。吹雪いて前方が見えなかったため、皆コワゴワになってしまっていました。
テン場まで行き、テントを張る。吹雪いていたため、目が痛いしテントは飛びそうになるし、やっとのことテントを張りました。17名の大所帯のため、テントは4張り!
小屋が経営してたおかげで、濡れた服やカッパ、手袋なんかを乾かすことができました。何しろ、雪上を転げ回ったので、カッパを着ていても下着まで水が浸透してたので。
ストーブの前に群がる群がる。今回はなんと快適!
4月16日
5時半起き。視界が悪く、一時待機。その後見違えるように晴天に恵まれ、例会メンバーは宝剣岳を目指し、私達は木曽駒ヶ岳を目指しました。夜のうちに積もった新雪は、慣れない雪歩きでは前に進まず…「もう少しや!」という会長さんの掛け声に励まされ、駒ケ岳山頂へ!眺めのなんと素晴らしいこと。
その後再びカールで雪上訓練。この時は、デッドマン、スノーバーなどを使い、ロープワークも学びました。
12:30のロープウェイで下山。
その後はやっぱり、名物ソースカツどんで締めくくりました。
| 山行期間 | 4/15-16 |
|---|---|
| メンバー | SKD(CL), ABE(SL), MTU, UTJ, TKD,WDZ,DTE |
| 山行地域 | 中央アルプス |
| 山行スタイル | 雪上訓練・アルパインクライミング |

春の例会、中央アルプス。千畳敷カールでの雪訓と、2日目はサギダル尾根から宝剣岳を目指す計画です。
4月15日(土)風雪
7時の始発バスに乗って、ロープウェイで一飛びに雪山に。どこでもドアのようです。
今年は雪が多い方で、この日の千畳敷は吹雪でまだまだ雪山!の環境。
ホワイトアウト気味の千畳敷を乗越浄土の下まで降りて、雪訓開始〜〜
メニューは、アイゼンなしの下降、滑落停止、スノーバーを使った支点構築など。


吹雪がどんどん強くなり、気温が高くて雨になるかきわどい感じでした。
ロシア付近の低気圧の影響で、この日は天気回復が見込まれないため、昼前に雪訓を切り上げ、先に下山するUTJさんをお見送りにロープウェイ駅まで戻り、正午。
宝剣山荘の幕営地を目指し、ホワイトアウトの千畳敷に再び降りる
が、雪訓を続けるABEパーティのいる地点は全く見えません。
地図を整地してコンパスの方向に進んでいくと、ABEさんたちの姿がぼんやり見えてきてホッとしました。
乗越浄土への沢筋は、午前中に何パーティか登っていましたが、積雪でトレースは消えていました。
宝剣山荘めざして張り切って直登気味に登っていきますが
最後の急登でバテバテ、先頭を代わってもらい…
13時10分、乗越浄土。
一緒に行動していたSGYパーティのメンバーも続々と上がってこられました。


山荘に着くと、なんと小屋が営業しておられ、トイレもお水も利用できることに。
強風の中テントを設営し、1時間くらいかかりました。

気温は比較的高いものの、朝まで強風が続きました。
4月16日(日)風雪のち快晴
4時起床、吹雪は止んでない。前夜から積雪が続いていたため、サギダル尾根は中止とし、朝食をとりながら待機しました。
だんだんと風が弱まり、空も晴れてきたので、山荘から宝剣岳を往復することとし、登攀準備開始。
7時10分出発。SGYパーティも、木曽駒をめざして行かれました。

雪は固まっているものの、新雪が溜まっている斜面はおそるおそるのトラバース

フカフカの下がガチガチで足が決まらず、なかなか進まない雪壁

背後に「は〜や〜く〜〜」という無言のプレッシャーを感じながら

7時50分、山頂

SKDリーダーに下降路を選定してもらい、露出している鎖を使って、カラビナスルーと懸垂で下降。



9時、山荘まで無事下山しました。
雪崩を心配していた千畳敷への下降路沢筋も、どんどん人が登ってきていました。
快晴で気温が高く、足裏に雪がつくので尻セードで一気に下降し、
降りたところで、雪訓の続きスタンディングアックスビレーの練習

12時30分のロープウェイで下山しました。
今回の例会では、悪天候における行動・判断など、春合宿に向けて各パーティ非常に良い訓練になったと思います。
雪山に行けば行くほど、日頃の訓練の大切さを感じます。
絶対に滑落しないこと、滑ってしまったらすぐ止めること。
大事な装備を残置しないこと、テント装備のコンディションを確認しておくこと。
基本に戻って、気を引き締めて春山に臨みましょう。


(SGYさんパーティのみなさんと)
| 山行期間 | 2017年3月24日(夜)~26 |
|---|---|
| メンバー | ASI,INK,UET,KSI,SOT,TST,TYK,MRJ |
| 山行地域 | 西穂高岳独標 |
| 山行スタイル | 卒業山行 |
西穂高独標
卒業山行で3/25にロープウェイ西穂高口駅~西穂高独標の往復、3/26には高山市を観光してきました3/25、天気は快晴、西穂高口駅の展望台では山々が雲に隠れることなく見渡すことができました。
風もほとんどなく順調に西穂山荘~丸山~独標手前まで到着、独標の岩場にさしかかったとき近くで見ると思ったより切り立っていて足がすくんでしまった。
何とか登りきって達成感と喜びもつかの間下りは登りよりも怖く、へっぴり腰になって下って行きそのあとは難なく下山




(9:35西穂高口駅→10:30西穂山荘→12:00独標→13:00西穂山荘→西穂高口駅)
下山後は穂高荘 山のホテルへ、温泉、夕食を楽しんだあと待ちに待った宴会へ!お酒もすすみよく覚えていませんがみんな楽しく語りあっていたはず!

次の日は朝露天風呂に入った後は高山市を観光し昼食に高山ラーメンを食べ帰阪。
今後はMチームとして皆が自分の目標に向かって進んでいくため、今回が76期という括りでの最後の参考となります。76期、またご教授くださったMチームの皆さん1年間ありがとうございました、またこれからもよろしくお願いいたします。
今回の山行は春合宿の剣岳を見据え歩荷・アイトレ訓練として中央アルプス宝剣岳を目指しました。
コースは北御所登山口よりうどん屋峠~宝剣山荘~宝剣岳の後ロープウェイで下山の予定でした。メンバーは春合宿を共に行う3名Abe、tkd、wdz
前日の前線通過による影響で大雪に
ガスってはいるが天気は悪くないのだが
そして、バスのチケット売り場では、、

なんと始発に続いて2便までも運行中止。
最速でも10:20発
話し合いの結果、歩いて登山口まで行く事に。先行き不安だ

そんななか2時間かけやっと北御所登山口に到着。
このタイムロスがどうでなるか、、、

ラッセル、ラッセル。ラッセるん♫
北御所登山口からここ蛇腹沢登山口まで夏山コースタイムでは30分程度だろうか。
しか~し実に2時間。
稜線、尾根歩きという事で今回はワカンを装備リストから外していた。
そして、、、

ラッセル、ラッセル ア〜〜ンド ラッセル。ふくらはぎ取れそうですが、ラッセル&ラッセル
う~ん、Abe氏強い!!

で、結局は、、
永遠に続くラッセル。しかし気力&体力は続くはずもなく精根尽き果て敢え無く清水平手前で敗退決定。テント設営。
本日の工程のたった三分の一程度でふくらはぎがK.O.

そして翌日。
良い天気。しかし敗退のため下山。



トボトボ。
朝も早い為バスも運行しておらず、またも歩いて駐車場まで。
途中2台のバスとすれ違う。今日は予定通り、いや臨時便も出たようだ。
最近敗退が多い気がする。
やはり雪山は天気&雪の状態で優しくもあり、全く歯型立たない事もある事を実感できる山行でした。
| 山行期間 | 20170325 |
|---|---|
| メンバー | WDZ, DTE |
| 山行地域 | 大山北壁 |
| 山行スタイル | アルパインクライミング |

2週間前に来た大山北壁
今回は先輩方なしの同期DTEさんとの冬山初個人山行。
夏山は何度か共にしたがさてどうなるか

まずは取りつきまで小一時間の登り
先週末の山行の疲れが残っているというDTEさん。かなり足取りがおもそう

今回の目標である弥山尾根
ここから見るとかなり立っている

いつものようにやっぱり晴天。
晴天記録更新中

前回はロープは出さなかったが、今回は練習もかねてロープで確保しながら進む


お隣の別山。
横から見ると尖ってます
が、実は別山からのトラバースがかなり怖く前回は一部またいで通過しました

雪が緩んでいて足元不安定&ピッケルの利きも悪い中、無事のぼってきました。

下りは6合目避難小屋より行者谷を尻セードで楽々~下山
今回は3月も終わりでしかも天気も良かったため雪が緩んでいて、頂上付近の日の当たる場所では雪面がピキピキと音を立てていたり、岩が崩れ始めたりとなかなかスリルのある状況で我々には少しピリ辛な山行になりました。
| 山行期間 | 3月17日夜~3月20日 |
|---|---|
| メンバー | HND(CL) UET |
| 山行地域 | 南アルプス |
| 山行スタイル | 冬季縦走 |

2月の「赤岳東稜」に続くHNDさんと行く冬季アルパインクライミング。
第二段は「鋸岳~甲斐駒ヶ岳」の縦走に3/18日からの3連休を利用し行ってきました。
3/17日


道の駅「南アルプスむら」で仮眠後、戸台登山口駐車場へ移動、午前7時「角兵衛沢出合」に向けスタート。戸台川の河原を延々と進む。積雪はないが大小の岩がごろごろし歩きずらい。


約2時間で出合に到着。一本入れてこれからの急登に備える。樹林帯からちらほら積雪が増え、角兵衛沢を積めあげるほどに雪が深くなる。今日は角兵衛沢のコルでBV予定なので、HNDリーダーの後を必死に食らいつく。午後1時予定より少し早くBVポイントに到着しゆっくり過ごす。



コル周辺は適当なBVポイントがなく、我々は岩の真下にツェルトを張る。この後到着したPTは我々の上部のコルの中央に張っていたが、スペースが少ないので要注意。
3/18日
午前3時起床。4時過ぎ今回の核心鋸岳の縦走が始まる。鋸岳(第一高点)への急登は、ノーロープで約30分程度で到着。まだ夜明け前で周りは暗く景色はよくわからない。風もあってそこそこ寒いので鹿窓に向けて一気に進む。小ギャップで今回初めて下降ためロープを出す。




ここからリッジ伝いにアップダウンを繰り返しながら進む。天気は良く視界も良好だが、如何せん自分は余裕がない。大ギャップを超え、中ノ川乗越を激下り、時々深雪を踏み抜きながら稜線を進む。三ツ頭を超え北東側に斜面をトラバースしたとき、ついにラッセル地獄に陥る。アイゼンからワカンに履き替えHNDさんの強烈な推進パワーで12時過ぎ本日のBVポイント六合石室に到着。(ラッセルは、リーダーに任せきりになりすみませんでした。交代できるよう体力つけます)
明日の行程が非常に長いため、快適な石室で早々に夕食を取り午後六時に就寝。


3/19日
午前2時起床。3時15分甲斐駒ヶ岳に向け出発。小屋から稜線に上がるルートを探すが、真っ暗闇で全く自分には判別できず、またもやルーファイをリーダーに委ねる。稜線にでると雪も締まりすこし歩きやすくなる。徐々に斜度も増し体がつらい。頂上直下の岩場では、ザックの重さもあり手こずる。先に到着したリーダーに遅れながらも午前5時甲斐駒ヶ岳山頂に到着。まだ日の出前で真っ暗なため、感激に浸ることもなく写真を撮りすぐに下山開始。


途中六方岩で休憩し、朝日が登り始めた稜線を気持ちよく駒津峰に向け進む。ここまで来ると少し余裕もでて南アルプスの景観を楽しむことができた。


駒津峰でひとしきりの記念撮影と要所要所で休憩をはさみながら、戸台の駐車場に午前11時到着し今回の全行程を終える。

この山行は、強靭な体力・折れない気力・的確な判断力・登攀やラッセルの技術力等総合的な登攀スキルが必要であり本当にいい勉強になった。自分に足りないものを身をもって理解できたので、今後のトレーニングの目標にすることとしたい。(UET記)
【行動記録】
3/18 戸台―角兵衛沢―角兵衛沢のコル泊
3/19 泊地―第一高点―第三高点―第二高点―中ノ川乗越―六合目石室泊
3/20 泊地―甲斐駒ケ岳―駒津峰―仙水峠―北沢峠―戸台
雑感・・・行動食の調達がむずかしい。疲れが増すと食欲が下がり甘いものとか受け付けない。
しかし、補給しないとエネルギー不足でさらに機動力が削がれる。
疲労困憊した時でも、食欲をそそり必要な栄養が補給できるものはないのか試行錯誤は続く...
| 山行期間 | 2017.03.11-12 |
|---|---|
| メンバー | TGA、ABe、WDZ |
| 山行地域 | 大山 |
| 山行スタイル | 大山 北壁 別山尾根・中央稜、弥山西稜 |

私とABeさんには1月のリベンジとなる大山北壁。
それでも多くのパーティーが入っておりトレースはばっちりあり、心配していたラッセル地獄も回避できました。が、二組の順番待ち。
今回は天気は抜群によく初日に別山尾根・中央稜バットレス、二日目に弥山・西稜にいってきました。
初日はガスが出ており取りつきが見えません
1ピッチをロープを出さずに登り上でビレイを何とかその横を通らせてもらい2ピッチ目よりロープを使用
1ピッチ目、2ピッチ目と高度が上がると斜度もドンドン厳しくなってきます。
いくつかの厄介なピッチを何とかやり過ごす
いよいよ別山尾根のピークが見えてきた最後のピッチ
稜線を先ずはTGAさんが渡り、その後肩がらみにてABeさんが渡りそのまま少し下降。そして今回の山行の核心部であるナイフリッジのトラバース!!
こっ怖~
途中稜線上で岩がボロボロで跨ぎながら、また50mロープでは渡れず途中か細い灌木で一度切って渡っていき、最後は少しの急登で一般登山と合流。
二日目。晴天。大山が一望できる。
カッコイイ~
本日は昨日よりグレードが低いということでのんびり。
取りつきまではやはり辛い。
その後も、先頭を歩き途中何か所かの急登を越えるとロープも使うことなくあっさり終了。所要時間は90分
下から見ると別山、弥山共に荒々しく切り立っていいるが、実際に登りこんなもんかという印象。
今回の山行では冬季登攀というより稜線歩きの難しさをしっかり味わえた内容になった。

| 山行期間 | 2017年3月3日夜~5日 |
|---|---|
| メンバー | KSM,TBS,UET,TKD,MSD |
| 山行地域 | 猫岳・輝山 (乗鞍岳周辺) |
| 山行スタイル | 山スキー |

3月5日~6日 乗鞍岳近くの猫岳と輝山に行ってきました。
メンバーはOBの笠松さん坪佐さんと植辻さん武田さんです。
天気が二日間とも最高で、昨年インナーを逆に履いたため?足が痛くなって一人敗退したのですが、今回は素晴らしい山行が出来ました。OBの方ともご一緒できたのは昔のお話が聞けて楽しかったです。