アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ!

| 山行期間 | 2020年12月29日〜12月31日 |
|---|---|
| メンバー | SKD、ITS、DIS、DIA、YSD、SMD、YAG、TKD、YMS、KSK |
| 山行地域 | 木曽駒ヶ岳 |
| 山行スタイル | 積雪期登山 |

当初の年間計画では80期Bチームの冬合宿は白馬岳の予定であり、その偵察山行も行っていた。しかし諸々の事情もあって1泊2日の山行となり、リーダー陣が色々と検討してくださった結果、行き先は木曽駒ヶ岳となった。ルートは上松A尾根のピストン。年末寒波の到来が予想されており、非常に厳しい山行になると覚悟して臨む事となった。
12/29(火)
21時半に三国ヶ丘、天王寺にそれぞれ集合し、車で長野県に向かう。今回は登山口に比較的近い場所で仮眠場所とさせてもらった。ちょうど雨が降りはじめていて、翌日からの山行に不安を抱きつつ仮眠をとった。
12/30(水)
6:00起床。まさかの本降りである。雨に打たれて冬山に登ると、あとで全てが凍りついてしまう危険が予測される。様子を見たが雨足は弱まらず、とりあえず登山口まで車を移動させる。前日まで比較的気温の高い日が続いたせいか、登山口は標高1085mほどだが雪が全く無く、相変わらず雨が降り続いていた。なかなか雨はあがらず、結局10時頃になって雨が弱くなったのを見計らって出発となった。

本日の予定は標高約2600mの8合目付近で、そこで幕営だ。眺望も何もない樹林帯の登山道を黙々と登っていく。まるで金剛山のようだ。

全然雪が無く、寒波も来ていないため気温が氷点下にもなっていない。僕はドライレイヤーにウールのベースレイヤー、薄手のフリースにハードシェルで登ったが、暑い。暑すぎる。比較的汗をかきにくいが、それでも上半身がしっとりする程度には汗をかいてしまった。他のメンバーではビシャビシャになるほど発汗する者もあり。

コロナの影響でトレーニングを充分に行えなかったメンバーもいて、1名が非常に疲労して遅れがちになるなどあり、全体のペースは上がらず。4合目くらいから登山道には少しずつ雪が見られはじめ、12:40頃5合目の金懸避難小屋のあたりでは少ないながらも全体に積雪していた。

気温も下がってきて風が強まり、軽く吹雪く様相。遅れが出たメンバーをここで待機していたが、身体がどんどん冷えていく。個人的には足指が寒さで痛くなってきて、全身を汗で濡らした者には過酷な汗冷えが襲ってきた。さすがに吹きっさらしで待機するのは低体温症を招く危険があり、避難小屋の入口に文字通り避難。しばらく待って全員が揃ったのち、リーダー陣でどうするか少し協議し、13:10目的地に向けて再出発となった。

しかし、どんどん寒さは増してくるし、積雪も増えてくるしでペース上がらず。ダラダラとした登りでなかなか辛い。

15:00で時間切れとなり、6合半と7合目の間、標高2220m地点で幕営適地を見つけテントを張った。

雪は降っておらず風も無かったが、テントを設営して入り込むまでの間も足元は無茶苦茶寒くて、足指がジンジンして痛い。寒さは痛さとして感じるという事を身をもって知った。テント内はやはり暖かく天国。

狭くて足がツりまくるのは玉に瑕だが、水を作り、夕飯を食べ、穏やかな時間を過ごした。今夜から明日にかけて、更に明日の午後以降は寒波襲来の影響で天候は荒れる見込み。不安を覚えながらの就寝となった。
12/31(水)
大晦日である。4:30出発のため3:00に起床。予想に反して夜間に雪はあまり降っていないようで、テント周辺の積雪状況はほぼ変わらず。気温も無茶苦茶下がってはいないように感じた。それでもテント内の結露は凍りつき、前日までに湿ったザックや濡れた衣類など、あらゆるものが凍っていた。気温はわからないが、−10数℃くらいではなかろうか。とにかく朝食を食べ、準備をして出発だ。アタック装備で登頂を目指すため余計な荷物はテント内にデポし、テント撤収もしなくていいので比較的時間に余裕はある。とは言え、アイゼンの装着に手間取ったりしているうちに予定時間を過ぎてしまい、結局4:40幕営地を出発。

それほど寒くないなと思ったのは最初だけで、足指と手指の末端が痛い。いや、体はそれほど寒いと思わないけれど、末端だけが異様に寒くて痛い。特に足指が痛くて堪らない。歩いていれば血行も良くなって痛みは消えるかと期待して出発したが、これがなかなか治らない。登るほど積雪は増えてくるわけで、トレースも無いため、ラッセルというほどの事はなくても先頭は結構キツイ。当然ペースは上がりにくい。そのため後続は体が暖まらない。

加えて遅れの出るメンバーもあり待機の時間も多くなる。全然血行が回復せず、足指の痛みがひかない。少し回復をしたかと思うと、あっという間にジンジン痛くなってくる。スリーシーズンであればジッと立っていても特になんて事ないが、気象条件が厳しい冬山ではただ立って待機しているのは本当に地獄だ。必死で靴の中やグローブの中で指を動かすものの、悲しいほどに痛みがひかないのだ。凍傷になってしまうかもという恐怖もあった。
6:30頃、ようやく1日目の目的地であった8合目に到着。標高は約2600m。ここらが森林限界となり、この先はいよいよ厳しい稜線だ。幸いというか何というか、意外に風は弱く、極限的な状況ではなかった。それでも稜線にそってプチラッセルをしながらトレースをつけていくのは、かなりキツイ。


息が上がる。雪面がクラストしていて歩きやすいかと思いきや、時々股まで強烈に踏み抜く。足指の痛みも取れない。キツイが、必死で雪にもがく行為は雪山を登っている事を実感させ、なんとか上まで行ってやろうと発奮する事にもなった。だが7:00。標高2640m地点でリーダーから撤退が告げられる。


かなり疲弊したメンバーもいるし、午後から天候が荒れる見通しもあるし、様々に状況を考えた上での判断であった。テントを撤収して安全に下りるには、残念ながら時間の余裕がなかった。もっと上まで行きたいし、できれば頂上も踏みたい。せめて木曽前岳くらいまで行きたい。しかし足指の痛みがずっと取れないままだったのでそれ以上進み続けるのが怖く、安堵する気持ちも同時にあった。
ともかく下りると決まればサッサと下りるに限る。自分たちで付けてきたトレースをたどり、黙々と下る。途中、8合目で集合写真を撮っていただいた。敗退記念の写真となったが、それが今の我々の実力という事だ。

いつか同ルートでリベンジしたいとの言葉も聞かれた。8:30頃、幕営地に帰着。テントを撤収して少しだけ休憩。冬山では休憩はゆっくりできない。寒くて堪らないのだ。快調な下りのペースでやっと回復していた足指も、テント撤収している間に再び痛すぎる状態に逆戻り。本当に止まっていられないというのを身をもって知った。

その後も良いペースで下り続け、10:30頃に金懸避難小屋へ。

晴れ間も出て日が差し、風もないので気持ち良い。標高を下げると気温も上がるため、もう足指は気にならなくなった(とは言え休憩などで止まっていると、やはりジンジン痛くなってくる)。前日と違っていたのは積雪。往路では全く見られなかった積雪が、登山口まで完全に続いていた。やはり昨晩でけっこう雪が降ったようだが、幕営していた高度ではあまり降らなかったという事だろう。そういうわけで下山は最終盤までアイゼンを付けたままだった。下りで遅れたメンバーも無事下山して、13:00登山口に帰ってきて終了。なにはともあれ全員が大きな怪我なく冬合宿を終えられて良かった。

第5ステージを担当してくださったリーダーの皆様、ありがとうございました。どのような状況になっても最大限のサポートをしていただいたと感じています。今回学んだ事を生かして第6ステージに向かいたいと思います。
| 山行期間 | 2020年11月7日〜8日 |
|---|---|
| メンバー | IKW(CL) SOT(SL) DIS DOM KSK TKD SMD YMZ KMR YSD |
| 山行地域 | 大阪周辺の地域 |
| 山行スタイル | アイゼントレーニング・歩荷 |

年末のBチームの冬合宿に向けて7日夜から8日にかけてアイゼントレーニングと歩荷訓練に参加させていただきました。
7日の夕方の集合時間からザワザワしだした。待ち合わせの駅を間違えるYSD私。忘れ物で取りに帰った2名。ありそうでなさそうな事態に発展。
計画書、連絡書をもっと見ないといけないと反省しました。
17時40分頃全員揃い本日の宿泊地に向かいます。
あれ、雨・・。降らないと思っていましたが雨具が必要な位に降り出しました。
到着し急いでテントを2張り張ります。
前回白馬岳で幕営した経験があるのでスムーズに6人用と4人用を張る事が出来ました。
すぐに晩御飯になります。先輩方がガスと大きなコッヘルを持ってきてくださったのでお湯を沸かしそれぞれが各自で食事を準備しました。
私はハヤシ飯というお湯を注ぐだけの簡単ご飯。早くて美味しくてお腹もいっぱいになります。
テントの外ではだんだんと雨が強くなりトイレに行くのも考える程に・・。
テントに入り山行の話で盛り上がりました。
20時になっても雨は止まず酷くなっていきます。天井からは水滴が滴り落ち何人か交代でタオルで拭いたりしました。
もう少し雨が止むまで待ちましょうという事で22時迄テントで話していました。
急いで4人用テントに移るも狭い空間での就寝準備に悪戦苦闘。
4人用テントで4人寝るのは当たり前なのかもしれないけど大変な物だと感じました。
色んな小技を教えていただきました。
翌日4時起床
暑くてシュラフカバーだけで寝ましたが明け方は少し肌寒く感じました。
ダウンジャケットを着たら丁度良かったかも、と思いました。
そそくさと片付けてお湯を沸かします。眠れました?とSMDさんに聞くと
あまり眠れなかったとの事。
端で寝ていたので水滴が染み込んで大変だったと思う。
私は帽子が濡れていました。朝ご飯に私はパンを食べて外に出てテント撤収します。
5時
暗がりの中歩くトレーニングをしました。ヘッドライトをつけて足元に注意しながら歩行します。
だんだんと明るくなってきて、次はワカンを冬季用手袋をはめたまま装置。これがなかなか難しい。イーッとなる気持ちを抑えながら個々に苦戦しながら装置しました。
アイゼンにしても同じですがこれを厳冬期の不安定な雪の中するとなると心配になります。

6時
猿回し。先輩方がロープを張ってくださりマッシャーを使いアイゼン歩行の練習をしました。下りは腰を低くして地面にアイゼンの爪が全体的に当たるように歩きます。
ピッケルの基本方向もあり実際に滑った時に自分が止めれそうなのか考えました。
次はロープなしでアイゼン歩行。ザクザク歩いて楽しかったですが帰ってからのアイゼンを洗うのには時間がかかりました。

9時頃から歩荷に入ります。
石を詰めて歩きます。私は前回は16kgだったので今回は20Kgに挑戦しました。階段では足が上がらず苦労しました。一歩一歩登っていきます。下りではバランスを崩しフラついたりしましたが、全員良いペースで下山できました。
他のメンバーは特にしんどそうな感じではなく、先輩方に関しては普通に重い荷物を担いでてすごいなぁと思いました。
これからも歩荷して体力をつけていきたいです。
ご指導いただきましたリーダー方、先輩方ありがとうございました。
YSD
| 山行期間 | 10月11日(日) |
|---|---|
| メンバー | SGY(CL) SZK(SL) AB(SL) TRN(SL) TNS(SL) TG(SL) KSK TKD SMD YSD KMR |
| 山行地域 | 蓬莱峡 |
| 山行スタイル | クライミング |
台風一過の日曜日、第2ステージでも訪れた蓬莱峡へ岩登りに行ってきました。
この日は我々Bチームとは別にMチームの先輩2名も来ていて、冬合宿に向けてアイゼンやハーケンを打つトレーニングをされていて、この先自分達もこの場所へ何度もくるのだろうなと思いました。
今回は3グループに分かれ、各グループにリーダーが2名付き指導していただく形でした。 午前は登攀と懸垂下降を2本行い、トップロープで安全を確保しながらビレイの練習をさせていただきました。
慣れない作業に力みながら、ロープを張り過ぎたり反対に出し過ぎていないか悩んだりしながら練習しました。
久々の懸垂下降も手順を思い出すのに苦戦しました。 今は落ち着いて確実にこなすことが第一ですが、本番は何ピッチもこなすので正確さとスピードが求められます。練習あるのみ!
午後は気温も上がり日差しを遮る物のない岩の上で汗ばみながら、リードで登った際の終了点の支点構築とオートビレイを教わり、特に印象深かったのがマルチピッチを体験したことでした。
狭いテラスに4人がひしめきあい、ロープアップしたロープを下に落としてしまったりしながら、本番の雰囲気を感じられたのではないかと思いました。 クライミングシューズではなく登山靴での登攀も経験し、最初は恐る恐るでしたが無事登る事が出来て少し自信がつきました。 密度の濃い一日に、頭も身体もクタクタになりましたが大変勉強になりました。
第4ステージの岩登りも残すところあと1回。ほんの少しですが岩に慣れてきたかなと思います。 リーダーの方々には懇切丁寧にご指導いただきありがとうございました。
(SMD)
| 山行期間 | 2020年10月25日 |
|---|---|
| メンバー | SZK(CL) SGY(SL) KNS(SL) TG(SL) TRN(SL) AB(SL) KSK TKD SMD YSD KMR YMZ |
| 山行地域 | 百丈岩 |
| 山行スタイル | クライミング |

早いもので第4ステージも本日が最終日。雨の剣山に始まったが、その他の山行は晴天続きで本日も快晴だった。
8:10に道場駅に集合。そこから百丈岩へ移動する。やぐら前でヘルメット、登攀具を身につけ、自己脱出の方法をリーダーに教えて頂く。今回想定したのは、トップが登っていてロープが半分以上出ている状態で、トップが落ちてしまい下ろすことが出来ない状態。その状態からビレイヤーが脱出して助けを呼びにいくとのこと。
一連の流れをリーダーから教えて頂くが、正直途中からうる覚えだった。3パーティーに分かれて練習する。とりあえず実践あるのみだ。最初の1回目は、やはり途中からわからなくなり、リーダーから手ほどきを受けた。2回目には、だいぶスムーズにできるようになっていた。次にやる時にもできるように時間がある時に練習が必要である。安全に岩登りを楽しむためにも覚えることが沢山ある。1つ1つ確実にできるように反復練習だ。
その後、各パーティーで昼食を摂ってマルチピッチの練習に移動する。私達は、東稜をフォローで登った。1ピッチ目のテラスは高度感もあって気持ちが良かった。2ピッチ目は出足が少し難しく感じたが、勇気を出していけば簡単に登れるのかもしれない。天気も良く、風も涼しく、とても気持ちが良いクライミング日和。前回の第2ステージの百丈岩の時は、中央稜を懸垂で降りて登り返そうとした途端に雨が降ってきたのを思い出した。今日は雨の心配はない。




その後、中央稜に移動して懸垂下降を1ピッチする。何回しても懸垂下降はロープをセットするのも下降するのも緊張する。もっと回数を重ねて練習する必要がある。家で出来ることは少しでもやっておきたいと思った。無事に懸垂下降を終えて、フィックスロープにしてオートブロックで自己確保して登り返した。16:00にやぐら前に集合ということもあり、登り返したところで登攀終了。片づけをして下山準備をしていると、ろうそく岩を登っているパーティーがいた。あんな所をリードして登ったら気持ちが良いだろうな、と思った。
やぐら前に到着したのは、私達が1番だった。全員帰ってきたのは16:20頃で、みんな充実した表情をしていたように思う。リーダーの方々から一言ずつ頂いて終了となる。岩登りの楽しさも感じたステージであったが、最後に自己脱出という事故に遭遇した時のことも教えて頂いた。楽しい事ばかりではなく、常に危険と隣り合わせなのだ、と感じた1日でもあった。本日もご指導いただき、ありがとうございました。(記 YMZ)
| 山行期間 | 2020年9月27日 |
|---|---|
| メンバー | AB(CL) HND(SL) KNS(SL) TG(SL) TRN(SL) DT(SL) YMZ KSK TKD SMD YG YSD KMR |
| 山行地域 | 烏帽子岩 |
| 山行スタイル | フリークライミング |

|
【烏帽子岩】
大阪、兵庫等の代表的なフリークライミングエリア。初中級向けの 日当たりがよく、天気がよければ真冬でも登攀できるそうです。逆 |
9月27日(日) 曇りのち晴れ
今日は初めてのフリークライミング。
シングルロープを使っての登攀です。
道場駅から15分ぐらいで、目的地、烏帽子岩に到着。思っていた
登攀の準備をし、集合。グループ分けが行われ、グループごとに行
【メニュー①】
ロープワーク 復習
ビレイ時の注意事項
(リードが落ちた場合)
私は第2ステージのクライミングは6月に1回しか受講してなくて
少し練習した後に、リードが落ちた場合、リードの落ちる距離や、
【メニュー②】
登る → 降りる → 違うコースを登る
これをひたすら繰り返す。



先輩達がリードを担当してくださり、ロープを頂上にはってくれま
軽々と登っていく姿を見て、すごいなーと思いました。
先輩達が頂上でロープを確保していただいたら、次は私たちが登る
先輩達がビレイを担当してくれるので、安心です。
実際に登ってみると、想像以上に難しかったです。 手や足を置く場所が無かったり、あったとしても僅かな窪みしかな
また、ルート取りも難しかったです。
下から先輩や同期が登るのをみて、「あの辺で、あそこに足をかけ
私と違って普段からジムでクライミングをしている同期は登り方も
一つのルートが終わると、ロープを回収して、次のルートへ。
天気も良かったため、気がつけば沢山の人がクライミングに来てい




グループごどに休憩をとり、休憩後もひたすら登る、登る。
気付けば14時過ぎ。ポツリポツリと人が帰り始め、あんなにたく
15時になると泉州以外は2パーティーほど。
「何時まで登れますか?」「まだ時間大丈夫ですか?」などの声が
Bチームはがんばり屋さんばかりで、登れるまで何度も何度も挑戦
登れない時はとても悔しそうで、「もっと練習して、リベンジした
それぞれにやり切った感があり、満足顔で帰路につきました。
今回はフリークライミングということで、「Bチームのみんなには
トップロープを何度もはり、ビレイを担当し、ルートを変える度に
ありがとうございました。
| 山行期間 | 10月16日(金)夜〜18日(日) |
|---|---|
| メンバー | SKD ICS KOS YOS TKD YMS KMR |
| 山行地域 | 後立山連峰 白馬岳 |
| 山行スタイル | ピークハント |

80期Bチームの冬合宿は北アルプス・白馬岳である。冬の本番に臨む前に偵察を行う必要があり、第4ステージの途中ではあるが、今回から第5ステージも並行して開始となった。
10/16(金)
先発組は21時に三国ヶ丘駅に集合して車に乗り合い出発。運転を交代しながら6時間半かけて2:30頃に長野県安曇野にある道の駅「松川」に到着し、屋根のある所に6人用テントを2つ張らせてもらい仮眠。後発組は23時過ぎに天王寺を出発し、4:30頃に合流。短い仮眠をとる。
すでに雨が降っており、山行中の天気が気にかかる。1日目は雨および雪、2日目は晴れとなる予報だがどうなるか…
10/17(土)
6:00起床。30分でテントを撤収し、ロープウェイ乗り場へ移動。8時のロープウェイ第1便に間に合わせるため車を走らせる。予報通り雨が降っているが、比較的弱い降り方で良かった…と思ったのも束の間、高い山の上の方はどう見ても真っ白である・・・明らかに雪が積もっているぞ!
今回は偵察山行で軽アイゼンも装備にはない。本当に行けるのだろうかと不安になる。
ロープウェイとゴンドラを乗り継ぎ、9:00頃栂池自然園駅に到着。ここから登山開始。

まずは天狗原に向けて樹林帯の登山道を登っていく。幸い雨はパラパラと降る程度だったが、標高があがるにつれて間もなく雪に変わっていった。
10:00天狗原に到着。広々とした湿原だが、厳冬期は全て雪で埋まって雪原になるとの事。ここでホワイトアウトになれば全く身動きがとれなくなってしまう。小高い所に小さな祠があったが、そういった雪に埋まらないものを目印にするので、しっかり覚えておかねばならない事を教えていただいた。
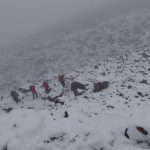
天狗原を抜け、乗鞍岳へ。ゴロゴロとした大きな石ばかりの登山道で、そこに薄く雪が乗っているものだからツルツル滑って怖い。かつガスもあって視界があまり良くないので、転ばないように慎重に登った。

11:00乗鞍岳頂上。

この頂上周辺も開けた台地状になっており、ここも雪とガスで真っ白になると非常に危険な場所だ。目印の大きなケルン?が聳えていた。このような場所から正しく次の目的地に向かうため、事前に地図上に方角を記入しておく有効性を教えていただいた。乗鞍岳を下りて白馬大池に向かうが、相変わらず雪の乗った石の上を進む道で、精神的に消耗した。個人的には全行程の中で乗鞍岳の登り下りが一番キツかった。

12:00頃、白馬大池に到着。当初の予定では1日目に白馬岳頂上まで登り、山頂直下の白馬頂上宿舎でテントを張る予定であったが、CLとSLが相談した結果、ここで本日の行動を終了しテントを張る事となった。気温はおそらく0℃〜−2℃くらいだろうけど、なにしろ雪が降り続いていて一面真っ白。ガスが濃くて視界が悪く、ここから上の状況がわからない。登りは登れても下りられない事にもなりかねない。予定通り歩けない事を残念に思いつつも、リスク回避の判断がされた事に正直ホッとした所もあった。
ともかくテントを協力して迅速に張り、荷物を放り込んで銀マットを敷く。1つのテントに7人全員が集まって湯を沸かし、温かい飲み物を飲んで、やれやれという思いで一心地つく事ができた。外は寒いが、火を焚けばテント内は天国である。
それから本日の振り返りや、これまでの山行の事など色々な話を聞かせていただいたり、皆んなで天気図を書いたりして夕食まで過ごした。これから冬山に挑戦していく上で身につけなければならない様々な事を教えていただいたので、少しでも自身を向上させられる努力をする必要性を強く感じたところである。
夕方頃には雪も完全に止み、遠くに青空も見られて天候回復の兆しあり。翌日は晴れが予測されているため期待である。
ありがたい事にテントの真ん中に寝かせてもらえたので、寒さに苦しむ事なくまずまず眠れた。
10/18(日)
80期Bチームは年度始めからコロナの影響を受けざるを得ず、実は共同テントを使うのが初めて。これまでの先輩方が当たり前にやってきたテント生活を経験できていなかったので不安に思っていた。
5:00から行動開始予定のため、4:00起床。
目覚めてすぐ可能な限り早くシュラフを収納袋にねじ込み、個人マットを畳んで、テント中央にスペースを作る。速攻で湯沸かし開始。SLから「起床後5分以内で湯を沸かしはじめられたので合格」との言葉があり、とりあえず一安心。ササッと朝食を終え、トイレを済まし、ザックをパッキングし、出発の準備を整える。
気温は体感で-5℃くらいか。スリーシーズンの靴では足指がジンジンし、止まっていると体か冷えて寒い。水溜りには氷が張っているが、星が瞬いていて天気は良さそうだ。風もない。
今日どこまで進むかは道の状況次第で決める事となり、テントに余計な装備をデポし、アタック装備で5:10テント場を出発。

前日の状況から考えて、正直、白馬岳山頂までは行けないと思って
思いの外サクサクと進み、5:45(2612mピーク)、6:25小蓮華岳に到着。もちろん標高があがってくると雪の量も増えてくるが、凍ってはいないのでアイゼン無しでも気をつければ歩ける。この状況を見て、白馬岳まで行く事が決まった。


天気は期待通りの快晴。白馬岳までの美しい稜線は雪をかぶり、山の中腹は紅葉の盛り。その下は雲海に埋められており、まさに絶景であった。日本海側からの風もほとんどなく、昨日からは考えられないような絶好の登山日和。
歩けば歩くほど白馬岳がスケール感をもって迫ってくる。
7:00三国境に到着。この辺りでは20cmほど積雪しているが、登山道は先行者のトレースもあり、靴が雪に埋まる事なし。



ここから標高差180mほど、やや斜度の増した道を黙々と登り詰め、7:45白馬岳山頂に到着。リーダーに記念写真を撮っていただいた。

個人的な事だが、僕にとっては初めての北アルプスである。それどころか入会前まで金剛山系か、遠くても大峰山系にしか行った事がなかったので、何か自分が場違いな所にいるような気がした。コロナの影響で年間計画は沢山の変更があり、80期としてもこれまでアルプスには行けなかった。初めてアルプスに行ったらスゴイ感動をするのかな、と思っていたのだが、案外そんな事はなく淡々とした気持ちであった。そういうものかもしれない。

さて、名残り惜しいが帰らなければならない。来た道を戻りながら、滑りそうな雪の見極め方や、体重のかけ方、雪崩斜面になりそうな場所、雪庇が張り出した時に稜線上のどこを選んで歩くか…などなど、様々な事を教えていただいた。体験は無いけれど、できるだけ雪山をイメージしながら歩かせてもらった。
8:30三国境、アップダウンを経て9:00小蓮華岳。戻るにつれて気温も上がり(体感で0℃〜3℃)、若干暑いと感じる場面もあった。
10:15白馬大池のテント場に到着。

テントを撤収してパッキングし、小休憩。乗鞍岳への登り返しはあるものの、あとは基本的に下るだけだ。
10:50白馬大池を出発。前日歩いた乗鞍岳の岩ゴロゴロ道からはほぼ雪が消え、遥かに歩きやすくなっている事に安堵した。
しかし、そのためか先頭のペースが上がりすぎ、後方を歩くメンバーを大きく引き離す事態に。1つのパーティとして動いているのでメンバーが視認できなくなるほど隊列が伸びるのは問題であり、先頭はもちろん間を歩くメンバーも、パーティとしてのまとまりを欠いていないか配慮し、ペースを調整したり声をかけあったりする必要がある。CLから注意を受け、反省しきりであった。以後、気をつけたい。
11:20乗鞍岳頂上。ここから下りも歩きにくい岩ばかりの道が延々と続いたが、無事に12:05天狗原に到着。
往路ではガスでほとんど見えなかった湿原が見渡せ、気持ちよく木道を歩く。
天狗原からは通常の整備された歩きやすい登山道。お喋りに花を咲かせながら樹林帯の道を快適に下り、13:10栂池自然園駅に無事到着。
紅葉の景色を楽しみつつ、ロープウェイで悠々と駐車場まで降りてきて14:10完全に下山となった。
毎度おなじみ、温泉でサッパリし、信州そばを食べ、高速道路をひたすら走って帰阪した。
これからはアイゼントレーニングや歩荷、1泊の冬山山行などを経験して、年末年始の冬合宿・白馬岳登山に臨むこととなる。
今回の経験も糧にして、是非とも合宿を成功させたいと思う。頑張ろう。
| 山行期間 | 2020年8月29日(土)夜~30日(日) |
|---|---|
| メンバー | OSM(CL)、HND(SL)、OKD(SL)、UET(SL)、UDZ(SL)、YMZ、KSK、SMD、TKD、YSD、YGI、KMR |
| 山行地域 | 大峯 |
| 山行スタイル | 沢登り |

第3ステージ 最終日。2回目の沢登り。
目指す沢は「下多古川」。 シモタコサワ? 初めて聞く名で調べてみると「山上ヶ岳から5番関への稜線から東
美しく、尚且つ、深みがなく、初心者の沢登りにうってつけの場所
当日、天気は曇りのち晴れ。 沢登り日和です。
週間天気予報では雲行きが怪しく、雨が降る可能性がありました。
私たち80期はコロナの影響でたくさんの山行が中止になってしま
そんな私たちの為、リーダーは雨が降った場合のバックアップとし
前泊組と当日集合組が合流し、6;00に下多古川へ。
沢のすぐ近くに駐車場があるため、沢靴を履いて、出発。
私以外のBメンバーは第1回目の沢登りに参加していて、今回が初
初めて履くフェルトソールにドキドキしながら入沢。




冷たくて気持ちいい。
気持ち良くても、フェルトソールに信頼をまだ寄せられない私は緊
時折、足元が不明瞭で意外と深かったり、大きな岩があったりとぎ
だんだん沢歩きに慣れてきて、沢靴のフリクションに安心できるよ
周りを見てばかりだと、足元が疎かになり、躓きそうになったり、
どんどん進むにつれ、岩場にでてきました。
流れが強くなっている場所や小さな滝になっている場所は、リーダ
Bチームのみんなは山の経験も私より豊富で運動神経もあり、どん
また、引き上げつつ、正しい引き上げられ方までしっかりとご教授



途中、読図の説明もしてくださいました。説明していただけると「
また読図に関してですが、私はBチームの後ろにいて、最後尾がチ
本日のビューポイントの琵琶の滝と中の滝は荘厳で美しかったです
特に中の滝に着く頃には太陽の光が差し込み、水面がキラキラ輝き
滝を見ながら、少し休憩をとりました。私はただただ「綺麗だなー
私は今まで生きてきて、滝を登ろうと思ったことはありません。私

中の滝を満喫したとは下山です。沢から外れ、登山道へ。
あっという間に下山できました。
楽しい山行と綺麗な沢のおかげで気分上々で下山し、駐車場で靴を
ヒル探しに関してですが、私はヒルがどこかにまだいて、車に持ち
ヒルに気分を害されましたが、その対価として、ヒルについて学ぶ
その後は柔らかいお湯の温泉に入り、チームリーダーおすすめのお
末筆になりましたが、リーダーの皆さま、ありがとうございました
たくさん学び、良い経験をさせていただきました。
今後ともご指導をお願いいたします。
また、一緒に歩いてくださったBチームの皆さまもありがとうござ
次回の山行もがんばりましょう。
(KMR記)
| 山行期間 | 2020年9月11日夜~13日 |
|---|---|
| メンバー | AB(CL) SGY(SL) SZK(SL) KSK SMD YMZ TKD KMR |
| 山行地域 | 四国 剣山~三嶺 |
| 山行スタイル | 縦走 |

|
大阪は、まだまだうだるような暑い日が続いている中、秋山?
新型コロナの影響でテン場やトイレの確保が難しく、南アルプス、
9/11(金) 21:30、 いつも通り三国ヶ丘駅に集合。
のはずだったが、
直ぐに気付いたことと、近くの駅で預かってもらえた為、
網棚に物を置く際は、くれぐれも注意されたい。
翌2:30過ぎに剣山登山口に到着した。
さすがに今回ばかりは宴会なしで即就寝。
パッキングがうまくなってきているのか、6:00起床で7:
出発直後より頂上はガスって見えない。
嫌な予感しかしない。
8:20 、コースタイム通りに剣山山頂に登頂。
案の定、景観は0、風が吹き荒れていて寒いだけだ。 証拠写真だけ撮影して、
9:00、次郎ギュウ登頂
雨も降りだした。。。
見どころの一切ない、ただただ修業のような山行が続きます。
10:20、丸石
11:55、高ノ瀬
 とうとう雨も大粒となり、稜線一つ見ることなく、14:00、
サブリーダーから、
雨、風は更に強くなり、雷も鳴り出したが、
避難小屋最高です!
お茶と食事でまったりし、18:00には就寝です。
2日目。
4:00起床、5:00前出発。
びちょびちょに濡れた登山靴やウエアを着るのは、
更に本日も朝からガスってます。。。
修業のような山行は続きます。
雨が降っていないことだけが、唯一の救いです。
7:30、三嶺登頂
ほんの一瞬だけ三嶺からの稜線が見えたことは、
直ぐにガスってきたので、下山開始です。。。
9:40、下山
下界は晴れてました。。。涙
まさに踏んだり蹴ったりです。
苦行の様な山行でしたが、辛い経験をしてこそ、
「卒業したら、天気のいい時に必ず来よう」と、
最悪の天候の中、引率して下さった諸先輩方、
|
| 山行期間 | 2020年8月13~15日 |
|---|---|
| メンバー | HND(CL)、DTE(SL)、MTD(SL)、YMZ、KSK、TKD、SMD、YGI、YSD |
| 山行地域 | 九重連山、由布岳 |
| 山行スタイル | 無雪期縦走 |

13日11時30分 長者原出発
お昼頃からの出発だった為か気温が高くとても暑くてこの先大丈夫かなぁなんて考えながら坊がつるに向かいました。
Bチームのメンバーが交代で先頭を歩かせていただきます。

13時30分 坊がつるテント場に到着しました。
広くお手洗いも近くにあり水道もあり良いテント場です。
早速テントを張りました。
あれだけ確認したのにペグを忘れてしまい石を拾いにいきました。
忘れものには注意と反省しました。
まずは大船山に向かいます。
14時 坊がつる出発
どんどん標高をあげていきますが荷物が軽いのでさっきより元気に歩けました。
15時30分 大船山到着
見事な景色に心が踊りました。



今回の縦走路には入っていない三俣山が綺麗にみえます。
17時00分 坊がつるテント場に帰ってきました。
なんとか法華院温泉に入れる事になり皆大喜び。

ここまで来て入らない手はないでしょうなんて声も聞こえてきました。
法華院温泉のバンガローはこないだの大雨被害で流されたと聞いていましたが大変な時に営業してくださり感謝しました。
山行中に汗を流せる事はありがたいですね。
良いお湯でした。

テント場に戻り次は食事の準備です。
私は簡単トマトソースのパスタを食べました。

皆でゆっくり話していると日が暮れていき少しずつ星が見えてきました。
ピカピカ光る新手の飛行機がいる!なんて声もちらほら。
さらにこの日は流星群の日だったようで初めてスペースシャトルのような大きな流れ星を見ました。
「わー!」と歓声をあげました。
これから星空を見る度に思い出す流れ星になるだろう。
3時起床 テント内でカレー飯というお湯を注ぐだけのご飯を食べます。
テントを素早く撤収して4時30分2日目行動開始です。
忘れ物がないかよく確認します。
ヘッドライトで歩きますがだんだんと明るくなり北千里浜辺りでは美しいモルゲンロートが見れました。
ここは見た事ないような景色が広がっていて不思議な感覚になりました。
6時30分久住別れに到着
7時天狗の城とどんどんピークを踏んでいきます。
天狗の城から見える御池には心が奪われました。
こんな山の合間に綺麗な池が存在する事が神秘的です。
7時10分九重連山最高峰の中岳。
三俣山や久住山、星生山とぐるりと見渡せます。
7時50分稲星山

8時30分久住山に到着しました。
山が違えば見える景色も違います。
9時に久住別れに戻ってきました。
最後の大きな登りの星生山に向かいます。
太陽が暑くなってきました。
暑いけれども良い景色がずっと見えるのはラッキーです。
皆頑張って登ります。
9時30分星生山到着

星生山は見る方角によって全然違う山に見えると何かに書いてありました。
ここからは下山になります。
200m程下ると少し登り返して11時 沓掛山に到着。
岩登りの要素もあり楽しかったです。
牧野戸峠登山口から登ってくる人も多いらしく沢山の人とすれ違うようになりました。
11時20分 牧野戸峠登山口到着
でもまだ終わりではありません。
駐車場までの道のりはまだ長いです。
車道を歩かないといけないと思ってましたが自然歩道が駐車場まで続いていたのでそちらを歩く事にしました。
灼熱の歩道歩きじゃなくて良かったと思いました。
12時30分長者原に無事到着
アイスクリームを食べて癒されました。
温泉にゆっくり浸かり次は待ってました!赤牛です。
縦走で疲れた後のお肉は格別でした。
皆も笑顔が溢れていました。
道の駅由布院の奥の方で寝ようとしていた所プレハブ小屋(工事中だった)の会社の方が現れご好意で小屋に泊まっても良いと仰ってくださっ
たそうな。
こんな事後にも先にも一度きりだと思います。
暖かい地元の方のご好意に感謝致します。
何か違う形で恩返ししたいと思いました。
本当にありがとうございました。
素早く片付け3時に出発します。
3時30分 由布岳登山口から登り始めました。
真っ暗な中ヘッドライトを照らしながら慎重に進んでいきます。
自分がどんな道を歩いているかもわからず気持ち悪い感覚がありました。
登りが始まりどんなキツイ傾斜だろうと思っていましたが登山道はとても歩き易くジグザグにひたすら登ります。
途中の小休憩では街の夜景が見えて綺麗でした。
ほとんどが山なので街の夜景も凝縮されていました。
さらにしばらく歩くと5時15分に西峰と東峰の鞍部「マタエ」に到着しました。
ここからまずは西峰に向かい御来光を見る予定です。
間に合うか!?皆ドキドキしながら岩場に喰らい付いていきます。
落石に気をつけながら距離を保ちどんどん登りました。
鎖場もありアスレチックで楽しいですが油断は禁物です。
5時40分頃由布岳西峰に到着。
写真を撮ったりワイワイとしているうちに誰かから「出た!!」と声が聞こえてきました。
お日様が顔をひょっこり出していました。
歓喜が湧き上がりました。
しばらく御来光を眺め御来光に安全登山のお祈りをし世界の平和のお祈りをし健康のお祈りをして・・
お祈りしすぎですね。
欲張るといけません。
由布岳の影を見れたのも嬉しかったです。
影由布ですね。
西峰から次は一旦マタエに下りて東峰を目指します。
東峰までの登りは特に危険はありませんでした。
6時30分東峰
写真を撮り少し休憩を入れて日向山経由で下山開始です。
下山道は歩きやすいと言える道ではなく急坂で転ぶといつでも怪我をしそうでした。
個人的には一番気を使ったルートでした。
日向山までの一部を私が先頭で歩かせていただきましたが広い樹林帯で地図とコンパスで確認しましたがわかりにくくこういう所で遭難が起こり易い
のだろうな、と感じました。
日向山8時30分着
樹々におわれた山頂で証拠写真を写しそそくさと退散。
山頂には1分しか滞在していないという。
そこから又ゆっくりと下山開始しました。
標高を下げる事に気温が高くなりジリジリと太陽に照らされました。
下の草原に帰ってきた時には素晴らしい景色が待っていました。
青い空に緑の草原、振り返るとさっきまで山頂にいたどっしりと美しい由布岳が地元の人々の安全を見守っているように見えました。
10時 下山
帰りはお楽しみの泥湯でドロドロ、ツルツルになり美味しい鳥天をいただき旅行気分を楽しみました。
今回同行してくださったリーダー陣の先輩方、楽しい企画を沢山織りこんでくださった渉外担当のお2人3日間共に歩いたBチームの仲間、ありがとうございました。
(YSD記)
| 山行期間 | 8月2日 |
|---|---|
| メンバー | OSM(CL)、OKD(SL)、HND(SL)、DTE(SL)、YMZ、KSK、SMD、TKD、YGI、YSD |
| 山行地域 | 比良山地 |
| 山行スタイル | 沢登り |

8/1(土)
今回は、Bチームとして初めての沢登り。コロナの影響もあって直前まで行先は確定していなかったが、金曜にメーリングリストで「白滝谷へ行きます」とCLよりメールがきた。
勿論、楽しみにしていた沢登りだったので嬉しかった。
前夜発で坊村の葛川市民センター駐車場へ。到着して各々飲み食いして寝床へ。前回の武奈ヶ岳より夜は寒く感じた。虫も思っていたより少なかったのでよく眠れた。
8/2(日)
5:00起床。天気は問題ない様子。各自朝食と着替えを済ませて5:47に駐車場を出発。
入渓地点を目指して登山道を登って行く。途中、ヒルがいそうな場所をCLから説明を受けた。今までBチームの山行で、御在所と武奈ヶ岳では、どちらもメンバーがヒルの餌食になっていた。今回も被害者は出るのだろうか。できれば自分はヒルの餌食にはなりたくないと思っていた。
奥の渡橋という入渓ポイントに到着して橋の所で沢靴に履き替えて、ヘルメット、ハーネス、登攀具を着用して6:30入渓。水に入った瞬間は冷たく感じたが、程よく気持ちがいい。他のBチームのメンバーも自然と笑顔が多かったように思う。最初はフェルトの感触を確かめながら歩く。水面からは足元の様子がわかりづらく、バランスを崩すこともある。水の流れが速いと足元が持って行かれそうになることもある。ちょっとした岩場を登る時もフェルトで滑りにくいので意外と登りやすかった。
読図については、わかりやすい目標物がある時は細目に現在地の把握に努めるようにと指摘があった。登山道を登るのとは違い、地形図や遡行図を参考にして登って行くのも楽しみであった。川の中を歩いたり、小滝を登ったり、高巻きしたりと色々と考えて登るのが楽しいだろうと感じながら登っていた。その分、危険も多くあるのだろうとも思った。登山に行く時は、初めての場所は勿論だが事前の下調べが重要になる。リーダーからも説明を受けていたが改めて感じた。
今回は安全第一ということで殆どの滝は巻き道を使ったが、他のパーティーでは滝を直登している人達もいた。直登も怖いだろうが、高巻きの沢靴や沢足袋で歩きづらく足元も安定しないので緊張することもあった。
途中休憩を1回して夫婦滝到着。夫婦滝では、ハーネスにロープをつけて滝壺向かって泳がせてもらった。気持ち良かった!
10:45に沢装備を解除して登山道を下山した。道が崩落している箇所があったり、渡渉箇所もあって下山も気を抜けなかった。途中湧水を飲むメンバーもいたが、その時なのか不明だがヒル1匹の餌食になった。幸い自分はヒル被害にはあっていない。下山中はリーダーの大好きな蛇に何度も遭遇した。実際捕まえようとしている姿を見てホントに好きなのだと思った。そして何とも頼もしい・・・
12:45駐車場に到着。
今回の沢登りは天候にも恵まれ、リーダーや先輩方のおかげで良い山行になったと思う。
他のメンバーもずっと笑顔だったように思う。暑い夏に涼を求めて沢登りも良いと思った。
5:47葛川市民センター駐車場(出発)、6:30奥の渡橋(入渓)、10:00夫婦滝、
10:45下山開始、12:45駐車場(到着)
(YMZ記)